ここ数年で、飲食店を取り巻く経営環境は大きく変わりました。
小麦粉や食用油、肉・魚・野菜などあらゆる原材料の仕入れ価格が上昇し、それに加えて光熱費も高止まりが続いています。
また、最低賃金の引き上げによる人件費の高騰といった社会的要因も重なり、以前と同じような価格設定では利益が出しづらくなっているのが現状です。本来であれば、原価の高騰に合わせた価格の見直しが必要になります。
しかし、客離れの懸念から、値上げに踏み切れずにいる飲食店経営者も少なくありません。実際、安易な価格改定は顧客離れのリスクを伴います。しかし、適切な戦略と準備を行えば、そのリスクを最小限に抑えられる可能性があります。
ここでは、飲食店が値上げをする際に客離れを防ぐ方法を、顧客心理と実践的な対策の両面から解説します。
飲食店が値上げを先送りするリスク
 飲食店が値上げをしないという選択を続けた場合、どのようなリスクが現れるのかを利益・サービス・人材・競争力の4側面から見ていきましょう。
飲食店が値上げをしないという選択を続けた場合、どのようなリスクが現れるのかを利益・サービス・人材・競争力の4側面から見ていきましょう。
利益率の悪化による経営基盤の不安定化
総務省が令和7年(2025年)6月27日に発表した消費者物価指数(2020年基準)によれば、生鮮食品を除く総合指数は110.3となり、前年同月比で3.1%の上昇が見られています。エネルギーを除いたコアコアCPIも同様に3.1%の上昇です。
参考:2020年基準消費者物価指数(東京都区部 2025年6月分中旬速報値)|総務省
これは、飲食店の経営に直結する原材料費の高騰が続いていることを意味しており、店舗運営における原価負担の増大が数値として現れています。価格を据え置いたままでは利益率が低下し、店舗の財務基盤そのものが不安定化するリスクが高まります。
また、資金繰りが厳しくなると、設備投資や新メニューの開発に充てる予算確保が難しくなります。結果、他店との競争において不利な立場に追い込まれることが懸念されます。
サービス品質低下による顧客満足度の悪化
多くの飲食店で、利益が圧迫されたときに行うのがコスト削減です。
特に効果が高いのが食材費の見直しですが、食材のグレードダウンや併用による品質変化が起こりやすくなります。また、人件費削減によるシフト調整や人員配置の見直しにより、接客人数の減少や提供スピードの低下といった影響が出始めます。
その結果、お客さまが感じる「いつもの美味しさ」や「心地よいサービス」に微細な変化をもたらし、気づかないうちに客離れを招く要因となる場合があります。とりわけ常連客は、味や雰囲気、接客の微差に敏感です。これまで培ってきた信頼を守るためには、サービスの質を維持するための適切な投資が欠かせません。
スタッフの労働環境悪化と離職率上昇
値上げを先送りして収益が圧迫されると、人件費の削減を目的としたシフト短縮や人員削減が実施されるケースがあります。
しかし、人件費の削減は即効性がある一方で、労働環境の悪化につながりかねません。
例えば、シフト削減を行うことで、少ない人数で店舗運営を行う必要が生じるため、一人ひとりの業務負担が重くなり、モチベーションの低下を招く恐れがあります。厚生労働省が発表した「令和6年 雇用動向調査結果の概況」によれば、2024年上半期における「宿泊業・飲食サービス業」の離職者数は643.7千人にのぼり、産業別では上位3位に入る水準です。
さらに、パートタイム労働者においては、同業種の入職率が18.3%と全産業で最も高く、人の出入りが激しい業界であることが明らかになっています。
参考:令和6年 雇用動向調査結果の概況|厚生労働省
元々離職率の高い飲食業界において、労働環境の悪化はさらなる人材流出を加速させる可能性があります。持続可能な店舗運営のためには、適切な価格設定による収益確保と、スタッフが働きやすい環境の両立が重要な課題です。
飲食店の値上げで客離れが起こる3つの理由
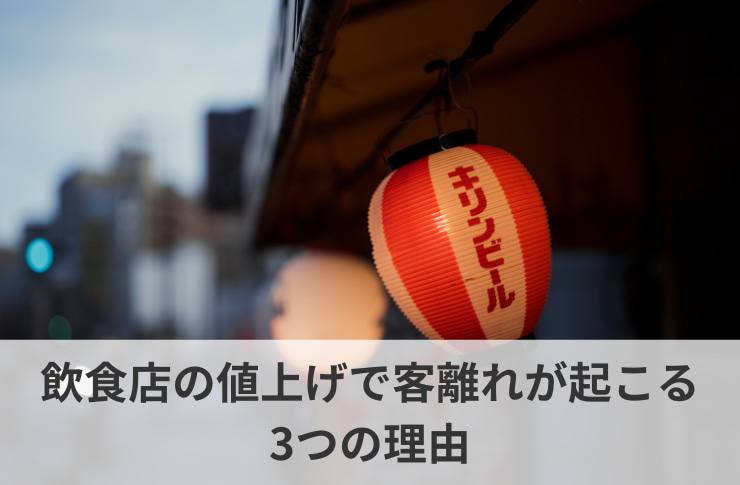 値上げによる客離れは、単純に料金が高くなったからという理由だけではなく、以下のような複雑な心理的要因が関係している場合があります。
値上げによる客離れは、単純に料金が高くなったからという理由だけではなく、以下のような複雑な心理的要因が関係している場合があります。
- 店舗に対する不信感
- 価格と価値が見合わないと感じる不満感
- より安い店を探したくなる比較心理
これらの心理的要因を理解することで、値上げを行う際に顧客の反応を予測し、適切な対策を講じることが可能になります。それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
店舗に対する不信感
世の中の物価高騰や原材料費の上昇といった動きを見ていれば、多くのお客さまは飲食店の値上げはやむを得ない状況だと理解できます。
しかし、値上げを行った際、適切な説明や理由付けがされていないと、顧客はその背景を推測できず、「ただ儲けたいだけでは?」という不信感を抱くことがあります。特に常連客ほど、店との心理的なつながりを重視しているため、突然の価格変更は関係性に影響する可能性があります。
例えば、「価格改定の理由が何も書かれていなかった」「いつの間にかメニューが高くなっていた」というような状況は、たとえ合理的な理由があったとしても、顧客にはネガティブな印象だけが残ります。結果として、来店頻度の低下や他店への乗り換えといった行動に結びつきやすくなるのです。
信頼関係が崩れると、その回復には時間がかかります。価格だけでなく誠実な説明がなされているかどうかが、客離れを防ぐ上での大きな分かれ道になります。
価格と価値が見合わないと感じる不満感
「この内容で、この価格?」という感覚は、飲食店を訪れた際の全体の満足度に直結します。
特に値上げの後は、料理の質や提供の工夫が従来と変わらなければ、多くの来店者が「割高になった」「前より魅力がなくなった」といった印象を与えがちです。値上げをした場合、お客さまは以前よりも高い対価を支払うことになるため、自然とより高い価値を期待するようになります。
しかし、料理の内容や味、サービスが以前と同じままであれば、コストパフォーマンスが悪くなったと感じられてしまうのです。食事の満足感は、味やボリュームだけでなく、見た目や盛り付けの印象にも強く影響されます。
実際に、佐藤真実・岸松静代らによる「盛り付けからみた色と嗜好に関する研究」では、コロッケ4個の盛り付けにおいて、「キャベツとパセリ」を添えたものが最も好まれた一方、「付け合わせなし」の盛り付けは最も評価が低かったという結果が示されています。つまり、同じ料理でも一手間加えた盛り付けや色彩バランスにより、価格に見合った価値を感じさせることができます。赤(プチトマト)や緑(パセリ)、黄(レモン)といった彩りを加えた付け合わせは、視覚的な満足度を高める効果があり、「外食らしさ」や「もてなし感」の演出につながります。
価格を上げるときこそ、視覚的な体験価値を高める工夫が必要です。見た瞬間に「丁寧に作られている」「特別感がある」と感じてもらえる料理は、価格以上の満足を提供する力があります。
より安い店を探したくなる比較心理
消費者は常に「より良い選択肢」を求めています。とくに飲食店に関しては、情報収集の手段が豊富で、SNSやGoogleマップ、ポータルサイトなどを使えば、近隣の他店の価格や評判はすぐに比較できます。
このような環境下で、値上げだけが目立ってしまうと、「他にもっと手ごろで美味しい店があるかも」と思わせてしまうきっかけになります。特にランチにおいては、100円、200円の差でも来店動機に大きく影響することがあります。値上げ後に新規顧客が増えにくくなる一因にも、こうした比較心理が関係しています。価格だけでなく、「選ばれる理由」が明確であるかどうかが、離脱を防ぐ重要なポイントです。

値上げによる客離れを防ぐ5つの効果的な方法

飲食店が価格を上げる際に、顧客離れを最小限に抑えるための実践的な方法を5つご紹介します。
- 売上目標の再設定と現実的な予測
- 事前告知と値上げ理由の説明
- 商品価値の向上と差別化戦略
- 段階的な値上げ
- テイクアウトや新サービスでの客層拡大
単に価格を変更するのではなく、信頼を守りながら価値を高め、継続的に選ばれる店舗となるための具体策を解説します。
売上目標の再設定と現実的な予測
値上げを実施する前に最も重要なのは、客数減少を見込んだ現実的な売上予測を立てておくことです。
特に重要なのは、「どの程度までなら客数が減少しても経営が成り立つか」を事前に計算しておくことです。例えば、平均客単価2,600円の居酒屋で、メニュー価格を一律10%値上げした場合を考えてみましょう。この場合、客単価は2,860円になります。
| 項目 | 従来の売上 | 値上げ後のシミュレーション |
|---|---|---|
| 平均客単価 | 2,600円 | 2,860円(10%値上げ) |
| 1日の平均客数 | 50人 | 40人(20%減少) |
| 1日の売上 | 130,000円 | 114,400円 |
| 月間売上 (30日稼働) |
390万円 | 343万円 |
上記の例では、客数が20%減少すると月間売上は47万円の減少です。もし原材料費の高騰により、月間のコストが50万円増加していた場合、値上げをしないと50万円の損失となるため、20%の客離れがあっても値上げの方が経営には有利という判断ができます。
さらに、損益分岐点の客数も事前に把握しておきましょう。上記の例では、新価格2,860円で1日46人以上の来店があれば、従来の売上を維持できる計算になります。
値上げによる客離れは、ある程度は避けられません。しかし、予測を立てておけば、客離れの状況に応じて適切な対応策を検討し、経営への影響を最小限に抑えることができます。
事前告知と値上げ理由の説明
価格改定を行う際には、変更の内容そのものよりも、どのように伝えるかが重要です。来店して初めて値上げに気づいたお客さまは、不信感を抱きやすくなります。
そうならないためにも、あらかじめ十分な期間を設けて、誠実にお知らせすることが欠かせません。告知の方法としては、レジ前への掲示、メニュー表への注記、店内アナウンス、公式SNSでの投稿など、複数の手段を組み合わせると効果的です。さらに、スタッフが一言添えるだけでも印象が大きく変わります。
伝えるべき内容としては、単に価格が上がるという事実だけでなく、その背景にある事情を丁寧に説明することが大切です。例えば、原材料費やエネルギーコストの高騰、スタッフの待遇改善、店舗運営の質の維持といった要素は、多くのお客さまにとって納得しやすい理由となります。
また、理由を述べる際には、経営者側の都合ばかりを押しつけるのではなく、これからも変わらず良い料理とサービスを提供していきたいという想いを添えることで、共感や理解を得やすくなります。価格変更を「知らせる」のではなく、「共有する」という姿勢が大切です。
商品価値の向上と差別化戦略
価格を上げるという判断をするのであれば、それに見合うだけの価値をしっかりと伝える必要があります。
値上げ後も変わらず足を運んでもらうためには、料理やサービスに対して納得できる理由が求められます。料理の味やボリュームといった基本的な要素に加え、盛り付けの美しさ、食器の選び方、料理が提供されるまでのスピード、スタッフの接客態度など、体験全体を見直していくことが大切です。価格以上の満足感を提供できれば、来店頻度を維持することは十分に可能です。
また、周囲の店舗と比べてどのような点が優れているのかを明確にし、その特徴を活かした打ち出し方を工夫することも効果的です。
例えば、地元の野菜をふんだんに使った季節のメニュー、健康や美容に配慮した栄養バランス、誰にでも親しみやすいメニュー構成など、自店ならではの魅力を形にしていくことが差別化につながります。こうした取り組みは、単に価格に対する納得感を高めるだけでなく、新規やリピーターの獲得にもつながります。
継続して来店したくなる理由がある店には、やがてその店を応援したいという思いをもつファンが生まれます。価格の変更をきっかけに、より多くのお客さまに深く愛される存在へと成長していくことができるのです。
段階的な値上げ
値上げをする際、一度に大きな金額を上げてしまうと、客離れにつながる場合があります。お客さまが価格の急激な変化に驚き、強い抵抗感や不満を抱きやすくなるためです。
このリスクを避けるためには、価格を段階的に見直していく方法が有効です。例えば、主力メニューの価格を一律に大幅変更するのではなく、メニューごとにタイミングを分けたり、少額ずつ引き上げていったりする方法があります。ワンコインのメニューを550円にする、セット価格を20円ずつ上げるなど、変化を小さく区切ることで、心理的な負担を抑えられます。
また、段階的に価格を見直すことで、客足や売上の変化を都度確認できるという利点もあります。値上げの影響を見ながら柔軟に対応できるため、無理のない範囲で価格戦略を調整し続けることが可能です。
テイクアウトや新サービスでの客層拡大
価格改定を行うタイミングは、単なる値上げにとどまらず、新しいサービスを打ち出すチャンスでもあります。
とくにテイクアウトやデリバリーの強化は、価格に敏感な層に対して、より柔軟な選択肢を提供できる手段として有効です。例えば、昼食時間帯にはお弁当スタイルのテイクアウトを用意し、夕方以降は少し特別感のあるセットメニューを展開することで、シーンや目的に合わせた利用が可能になります。外食を控えたいと考えている方にも、自宅で店の味を楽しんでもらえる機会が生まれます。
また、スタンプカードやポイント制度、LINE登録特典などを導入することで、来店頻度を高めたり、紹介による新規顧客の獲得にもつながります。価格を見直すだけで終わるのではなく、新しいサービスの提案によって選択肢を広げることが、顧客の離脱を防ぐ大きな支えとなります。
これまでとは異なる層との接点が生まれれば、結果として客数や売上全体の底上げにもつながっていきます。
【飲食店向け】値上げによる客離れはスマセルが解決

価格改定の決断をしたあとも、経営者としてはできる限りお客さまの負担を和らげたいと考えるものです。
そのためには、単に値段を上げるだけでなく、同時にサービスの質を維持したり、業務効率を改善したりする工夫が欠かせません。そのひとつの具体策として注目されているのが、スマセルのQRオーダーシステムです。
お客さまがテーブルでスマートフォンを使って直接注文を行うこの仕組みは、スタッフの業務負担を軽減するだけでなく、注文の待ち時間短縮や提供スピードの向上にもつながります。
オーダー業務の効率化による人件費削減
飲食店の現場では、注文を取るためだけに人員を割かざるを得ない場面が少なくありません。
ピークタイムになれば、ホールスタッフは満席のテーブルを何度も行き来し、注文の聞き取りに追われます。その結果、配膳や片付け、接客への気配りが後回しになってしまい、サービス全体の質が下がることにもつながります。
スマセルを導入すると、お客さまが自身のスマートフォンを使ってメニューを確認し、その場で注文まで完了できるようになります。これにより、ホールスタッフは注文対応に割いていた時間と労力を、他の業務に充てられるようになります。例えば、2人で回していたフロア業務を1人で対応できるようになる、注文ミスが減ることで確認作業が不要になる、といった具体的な業務効率の改善が期待できます。これらはすべて、時間あたりの人件費の削減に直結します。
また、忙しさによる接客のばらつきが減ることで、サービス品質を一定に保ちやすくなるというメリットもあります。さらに、業務が整理されることで、スタッフが余裕を持って働けるようになり、職場環境の改善にもつながります。人件費を抑えるだけでなく、働きやすさと満足度の両立を目指せる点も、スマセルの大きな利点です。
まとめ
飲食店にとって、値上げは避けて通れない経営判断のひとつです。
しかし、お客さまの反応や客足への影響を考えると、なかなか踏み切れずにいるという声も少なくありません。値上げによる客離れを防ぐには、価格に見合う体験を提供することが不可欠です。メニューの工夫や盛り付け、接客対応の改善など、細部にわたる取り組みが顧客の納得感につながり、結果としてリピーターの定着やファンの育成にもつながります。
また、今後の人手不足やコスト増を見据えるなら、業務の見直しにも着手しておくべきです。注文業務の効率化を図るスマセルは、少人数体制でも一定の接客品質を維持しながら、人件費を抑え、現場の負担を軽減する手段として、多くの飲食店で導入が進んでいます。値上げという選択を機に、店舗の運営体制を一段と整えていくことは、長期的に見て大きなプラスとなります。スマセルでは、導入前にしっかりと運用設計の相談ができるため、自店の営業スタイルに合わせた活用方法を検討できます。
値上げを検討している飲食店経営者様は、まず必要な見直しを整理しながら、こうした仕組みを組み合わせることで、売上の確保とサービスの維持を両立させる道を模索してみてはいかがでしょうか。

