飲食店の集客を考えるうえで避けて通れないのが、昨今の市場環境の大きな変化です。
スマートフォンやSNSの普及により、消費者の行動パターンは「事前にネットで調べてから来店する」スタイルに変化しています。外食への価値観も多様化する中で、従来の集客方法だけでは新規顧客の獲得が困難になっています。
また、競合店の増加や人口減少により、限られた顧客を巡る競争も激化しています。こうした状況を打開するには、時代に合った効果的な集客戦略を選び、限られた予算の中で最大限の成果を上げることが不可欠です。
ここでは、飲食店が直面している集客の課題を整理し、現状分析から導き出す最適な施策を解説します。
飲食店における集客の現状と課題

日本の飲食業界を取り巻く現状と、集客における代表的な課題を解説します。
- 人口減少による市場規模の縮小
- デジタル化の進展とSNSの影響力拡大
- テイクアウト・デリバリー需要の定着
それぞれが単独で影響しているのではなく、さまざまな要素が絡み合って、集客を難しくしています。背景と影響を詳しく見ていきましょう。
人口減少による市場規模の縮小
総務省統計局の人口推計総務省統計局の人口推計(2024年10月1日現在)によると、日本の総人口は1億2,380万人です。前年と比べて約55万人減少しており、これで14年連続の人口減となっています。
参考:人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)|総務省統計局
また65歳以上の割合は29.3%と過去最高を更新し、15歳未満は11.2%まで低下しています。さらに、内閣府によると、65〜74歳が12.5%、75歳以上が16.8%と詳細が示されており、今後も高齢化率は上昇すると見込まれています。
人口減少と少子高齢化は、飲食店にとって潜在顧客の減少と客層の変化を招く可能性があります。そのため、世の中の変化に合わせて、ターゲットやアプローチ方法を調整していく必要があります。
デジタル化の進展とSNSの影響力拡大
スマートフォンの普及とオンラインサービスの発展により、飲食店を選ぶ際はまずネットで情報収集することが一般的となっています。
そのため、料理が美味しくて接客が良くても、オンライン上で情報が不足していたり、レビューが悪かったりすれば、調べている人に十分な情報が届きません。結果的に、情報が充実していたり口コミの良い他店を選んでしまい、実際に来店してもらえる可能性は大幅に下がってしまいます。
また、最近では、InstagramやTikTokといったビジュアル中心のSNSも影響力を増しています。文字や画像だけでは伝わりにくい、料理や店内の雰囲気を感覚的に伝える力が強く、店の知名度を高め、来店したい気持ちを直接後押しできます。
このように、デジタル化が進む現代では、従来のポスティングや声かけといったアナログの集客方法だけでは、効果的な集客が難しい場面が増えています。
テイクアウト・デリバリー需要の定着
コロナ禍をきっかけに普及が進んだテイクアウトやデリバリーは、感染症が落ち着いた現在も多くの方が利用しています。
特に、在宅勤務をする人や共働き家庭においては、調理時間を短縮したいニーズの高まりが、この需要を下支えしています。また、一人暮らしの若年層や高齢者世帯でも、手軽に多様な料理を楽しめる手段として定着しています。
実際に、総務省によれば、現在もテレワークを継続している人の多くは、食料品・日用品の買い物・外食について外出頻度が減少し、その代わりに自宅近くやオンラインでの購入頻度が増加しています。
参考:令和5年度 テレワーク人口実態調査|総務省
この傾向は、外食やテイクアウトの利用にも影響を与え、「外に出るよりも手軽に購入・注文したい」というニーズを強めています。
そのため、従来の集客だけでは顧客のニーズを満たすことが難しくなり、テイクアウトやデリバリーに対応していない店舗は、潜在的な売上機会を逃してしまう可能性が高まっています。
飲食店の集客力向上は現状把握から始まる
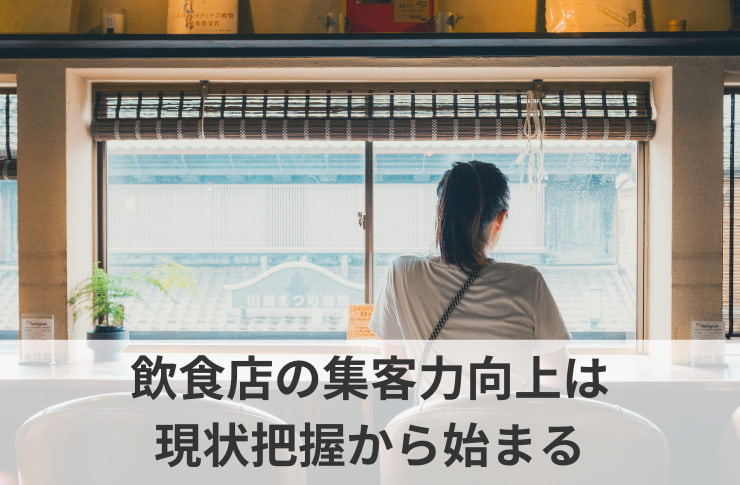
時代の変化に合わせた集客を行うには、感覚に頼らず数値で現状を把握することが大切です。特に以下の内容については、集客力の向上につながる可能性の高い項目です。
- 客層・売上・人気メニューの現状分析
- 自店舗の現状分析と強み・弱みの把握
- ターゲット層の明確化
- 顧客ニーズとトレンドの把握
それぞれ詳しく解説していきます。
客層・売上・人気メニューの現状分析
日々の営業で「なんとなく売れている」と思っているメニューや客層も、実際にデータで確認すると違う傾向が見えることは珍しくありません。
忙しい現場では注文頻度の高いメニューが印象に残りやすく、利益貢献度の高いメニューを見落としがちになるためです。感覚と実際のデータに乖離があると、収益性の低いメニューを看板商品として推してしまったり、実際の優良顧客層を見誤って適切でないサービス改善を行ったりして、売上機会を逸失するリスクがあります。
正確な現状分析のためには、顧客軸(年齢層・性別・来店時間帯・来店頻度など)と商品軸(メニュー別売上・利益率・注文回数など)の両面から、売上データを体系的に分析し検証することが重要です。
しかし、膨大な売上記録を手作業で整理・分析するのは現実的ではありません。そこで、POSシステムの活用が有効です。POSシステムを活用すれば、「誰が・いつ・どこで・何を」購入したかが自動記録され、顧客軸と商品軸の両面から詳細な分析が効率的に行えます。
自店舗の現状分析と強み・弱みの把握
効果的な集客戦略を立てるには、まず自分の店の立ち位置を正確に知ることが不可欠です。
そのために役立つのが、SWOT分析(Strength=強み、Weakness=弱み、Opportunity=機会、Threat=脅威)です。
Strength(強み)
- 他店にはない魅力や優位性
- 例:駅から徒歩3分の好立地、地元で評判の看板メニュー、常連客に支持される接客スタイル
- 強みはお客さまに一番伝えたい魅力となり、広告やSNSで前面に出すべきポイントです
Weakness(弱み)
- 改善の余地がある部分や課題
- 例:客席回転率が低い、平日昼間の稼働率が低い、スタッフによるサービス品質のばらつき
- 弱みは隠すのではなく、改善によって強みに転換する発想が重要です
Opportunity(機会)
- 外部環境から得られるプラス要素
- 例:近隣に大型オフィスビルの開業予定、地域イベントの増加、新しい配達サービスの普及
- 機会をつかむためには、先読みした準備と対策のスピードが鍵です
Threat(脅威)
- 外部環境からもたらされるマイナス要因
- 例:競合店の新規出店、原材料価格の高騰、人材採用難
- 脅威を緩和するために、仕入れ先の分散や価格の見直しなどの対策が必要です
このように店舗の強みと弱みを4項目で整理することで、何を伸ばし、何を補うべきかが明確になり、集客方法の優先順位がはっきりします。しかし、SWOT分析は要素を洗い出すだけでは意味がありません。重要なのは、4つの要素を掛け合わせた「クロスSWOT分析」で、具体的な戦略オプションを検討することです。
例えば、「駅近立地」という強みと「近隣オフィス開業」という機会を組み合わせることで、ランチタイムの強化という施策を立てられます。このようにSWOT分析で整理した内容を戦略に落とし込むことで、感覚的な判断ではなく論理的で効果的な集客施策を構築できるのです。
ターゲット層の明確化
集客戦略を成功させるには、誰に向けてお店の魅力を伝えるのかを明確にすることが欠かせません。
「老若男女すべての人に愛される店」を目指すと、結果として誰にとっても特別感のない店になってしまい、印象に残らない発信になってしまうことが多いからです。そこで、現状分析で得られたデータをもとに、自店にとって最も価値の高い顧客層を絞り込みます。
例えば、平日ランチの時間帯に多く訪れる近隣オフィス勤務の女性、週末に家族連れで利用するファミリー層、夜に来店する若いグループ客など、具体的な人物像を描くことが重要です。年齢層や性別、来店目的、平均利用金額、来店頻度などを細かく設定することで、その層に響くメニューやサービス、広告の打ち方が見えてきます。
さらに、ターゲット層が普段どのような情報源から飲食店を探しているのかも把握しておきましょう。InstagramやTikTokのようなSNSをよく使う層なのか、Googleマップや食べログなどの検索サービスから探す層なのかによって、集客チャネルの選択も変わります。
こうしてターゲット層を明確にすると、限られた予算でも効果的に集客ができ、メニュー開発やキャンペーンにも一貫性が生まれます。
顧客ニーズとトレンドの把握
顧客の声を取り入れたマーケット調査は、飲食店が成長するために欠かせません。
お客さまの意見や要望を理解し、それに基づいてメニューやサービスを改善することで、満足度を高め、競争力を強化できます。
顧客の好みやニーズの把握
お客さまが何を求めて来店するのかを正確に知ることから始めます。
アンケート、フィードバックフォーム、口コミの内容を定期的に整理し、好評点と改善点を洗い出します。得られた情報をメニューの改良や提供方法、価格帯の見直しに反映すれば、飲食店の集客方法がより効果的に機能します。
顧客との関係を深める
お客さまからいただいた意見や要望をまとめ、改善した内容を店頭やSNSで発信することで、声が反映されている実感が生まれます。
こうした対応は、信頼関係を築き、再来店の理由を増やすことにつながります。
競合分析と差別化
顧客の不満やまだ改善されていない要望は、競合が十分に対応できていない部分を明確にします。
店舗の強みと重ね合わせることで、他店との差別化ポイントを明確にでき、比較検討の段階で選ばれる理由を作れます。
新商品・サービス開発への活用
顧客の声を基に、試食会や限定メニューなど小規模なテストを行い、反応が良いものを定番化します。
実際の意見を起点にすることで、投資効率を高めつつヒットの可能性を高められます。
将来需要の予測と継続的な改善
口コミの内容や売上データを継続的に確認することで、季節や生活習慣の変化によるお客さまの好みの変化をつかめます。
変化の流れを把握しておけば、メニューやサービスの見直しをタイミングよく行えるようになり、競合より先に新しい提案を出すことが可能になります。トレンドを把握することで、日々の改善が点で終わらず線となり、お店の強みとお客さまの期待が重なる機会を計画的につくれます。
飲食店の集客力を向上させる5つの方法

現状分析で把握した課題を解決し、集客力を向上させるための具体的な施策を紹介します。
特に以下の5つの方法は、限られた予算でも効果が期待できる実践的な手法です。
- ポータルサイトの掲載と情報の最適化
- ポスティングで商圏内の認知度を高める
- SNS・Web発信による認知度向上
- 多言語対応でインバウンド市場を開拓
- QRオーダーシステムで若年層のニーズに対応する
それぞれの手法で効果を最大化できるよう詳しく確認していきましょう。
ポータルサイトの掲載と情報の最適化
食べログ、ぐるなび、ホットペッパーグルメなどの飲食店ポータルサイトは、高い集客効果が期待できます。
公正取引委員会の調査によれば、外食市場にはおよそ80万店舗の飲食店があるとされ、ポータルサイトの加盟店舗数も年々増加しています。2017年3月末には約57万店舗、2019年3月末には約69万店舗に達しており、利用の広がりが数字からも明らかです。
また、同調査の消費者アンケートでは、飲食店を利用する際に電話やFAXよりもポータルサイト経由で予約することが多いと答えた人が72.1%にのぼっています。これは、消費者がオンライン経由で店舗を選び、予約まで完結させる行動が一般化していることを示しています。
参考:飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について|公正取引委員会
そのため、ポータルサイトは単に情報を載せておくだけでなく、店舗情報やメニュー、価格などを常に最新に保つことが重要です。営業時間や定休日、季節メニュー、料金改定などが実際と異なれば、ユーザーの信頼を損ない、来店機会を逃してしまいます。
また、料理や店内の雰囲気が伝わる高品質な写真の掲載、定期的な更新、レビューへの返信も集客効果につながります。
ポスティングで商圏内の認知度を高める
ポスティングは、お店の近くに住んでいる人や、近隣で働いている人へ、直接情報を届けられる地域密着型の集客方法です。
特に店舗から徒歩圏内や自転車圏内の潜在顧客に情報を届けるには効果的で、折込チラシやWeb広告とは違い、手に取って読んでもらえる機会が多いのが特徴です。効果を最大化するためには、ただチラシを配るのではなく、配布エリアの選定とターゲットに合わせたデザインが重要です。
例えば、平日ランチを強化したい場合は、オフィスや事業所の多いエリアに配布し、メニュー写真やクーポンを大きく掲載します。週末の家族利用を狙うなら、住宅街やマンションエリアに向けて、子ども向けメニューやファミリー割引の情報を打ち出すと効果的です。
また、季節やイベントに合わせた内容にすることで、来店動機を作りやすくなります。花見や地域祭りの時期には特別メニューを、年末年始や大型連休前には予約受付や持ち帰り商品の案内を盛り込むと反応率が上がります。
配布後には、来店時に「チラシを見た」お客さまの人数や使用クーポン数を記録し、検証を行いましょう。こうした検証を繰り返すことで、より精度の高いポスティング戦略が構築できます。
SNS・Web発信による認知度向上
飲食店にとって、SNSは今や欠かせない集客ツールです。
飲食店ドットコムの調査によれば、飲食店の約9割が何らかのSNSアカウントを開設しており、そのうち98.6%が外注せず自店で運用しています。投稿内容として最も多いのは「営業日や営業時間の告知」(79.6%)、次いで「仕入れ食材や新メニューの告知」(72.9%)、「キャンペーン情報」(54.2%)が続き、多くの店舗が基本的な情報発信を中心に行っていることがわかります。
中でも注目すべきは、Instagramの集客効果です。集客や認知拡大において効果を実感した店舗は48.3%にのぼり、半数以上が今後さらに注力したいと考えています。写真や動画を通して料理や店内の雰囲気を直感的に伝えられるInstagramは、飲食店にとって相性の良いプラットフォームと言えるでしょう。
参考:飲食店経営に関する調査レポート|飲食店ドットコム
このように、SNSは単なる情報発信の場にとどまらず、来店を検討したり予約といった次のアクションへとつなげる重要な接点となっています。
多言語対応でインバウンド市場を開拓
日本政府観光局(JNTO)によると、2024年6月の訪日外国人客数は約338万人で、前年同月比7.6%増と過去最高を記録しました。上半期全体では2,152万人に達し、コロナ前の水準を大きく上回っています。
参考:訪日外客数(2025年6月推計値)|:日本政府観光局
この状況は、飲食店にとって新たな顧客層を獲得する大きなチャンスです。外国人客を取り込むための最初のステップが多言語対応です。英語・中国語・韓国語のメニューやアレルギー表示を用意するだけで、外国人客は安心して来店できるようになります。
さらに効果的なのは、GoogleマップやTripadvisorなど外国人旅行者がよく使うサイトに、多言語で店舗情報を掲載することです。旅行計画を立てる段階で見つけてもらいやすくなり、来店候補に入る可能性が高まります。
また、QRコード注文システムを導入すれば、言葉が通じなくてもスムーズに注文ができ、忙しい時間帯でもスタッフの負担を軽減できます。インバウンド対応のメリットは売上増加だけではありません。外国人客が帰国後にSNSで店舗を紹介してくれれば、海外での知名度向上や将来的なリピーター獲得にもつながります。
そのため、多言語対応は、成長が見込まれるインバウンド市場への重要な投資といえます。
QRオーダーシステムで若年層のニーズに対応する
近年、10〜30代を中心に「非接触」「スマホ完結」へのニーズが急速に高まっています。飲食店選びの際も、注文や会計のスムーズさが評価の基準になりつつあります。
そこで注目されているのがQRオーダーシステムです。QRオーダーシステムは、スマートフォンでQRコードを読み取るだけで、メニュー確認から注文・支払いまでを手軽に行えるシステムです。QRオーダーシステムは、店舗側にとっても、混雑時の注文待ち時間短縮や聞き間違い防止による効率化、注文データの活用によるメニュー改善など、多くのメリットがあります。
また、多言語対応機能を備えれば、外国人客にも安心して利用してもらえるため、インバウンド対策としても有効です。
スマセルで飲食店の集客力を大幅に向上

スマセルは、お客さまがスマートフォンでテーブルに設置されたQRコードを読み取るだけで、メニュー閲覧から注文・決済まで完結できるセルフオーダーシステムです。
専用端末の設置が不要なため、初期費用を大幅に削減でき、導入ハードルの低さから多くの飲食店で選ばれています。
また、スマセルでは、注文・会計・販促を一元化することで、飲食店の集客力と売上を同時に引き上げます。
1. 新規顧客の獲得を支援するセルフオーダー
アプリのダウンロードやパスワードの入力など面倒な手間は一切なく、QRコードを読み取るだけで簡単に注文できるため、デジタルに慣れた若年層の集客に効果的です。
待ち時間の短縮により顧客満足度が向上し、口コミやSNS投稿による自然な集客効果も期待できます。
2. データ分析による戦略的集客
POSシステムとの連動で、顧客の注文履歴や来店パターンが分析可能です。
人気メニューや客層の傾向を把握することで、効果的なターゲティング広告や集客キャンペーンの企画立案ができます。
3. LINE連携による継続的な集客
店舗のLINE公式アカウントと連携、販促アプリもあり、精度の高い情報配信で集客機能も備えています。一度来店したお客さまにクーポンやイベント情報を直接配信することで再来店を促進できるため、リピーター獲得による安定した集客基盤を構築できます。
4. インバウンド集客の強化
直感的な操作と画像を見て注文できるため、増え続ける外国人客にもしっかり対応ができます。多言語対応も可能なため、外国人観光客が安心して利用できる環境を整えることで、インバウンド需要の取り込みと新たな集客チャネルの開拓が可能になります。
5. 集客施策に集中できる環境づくり
オペレーションの自動化により人手不足を解消し、スタッフがより質の高い接客に専念できます。また、経営者は浮いた時間を効果的な集客戦略の立案やマーケティング活動に充てることができ、持続的な集客力向上につながります。
まとめ
本記事では、飲食店経営において欠かせない「集客力の強化」と「業務効率化」という2つの課題に対し、スマセルがどのような解決策を提供できるのかを具体的にご紹介しました。
SNSやWebを活用した認知度向上、多言語対応によるインバウンド市場の取り込み、QRオーダーによる若年層へのアプローチなど、時代に合った集客戦略はもちろん、セルフオーダーやPOSシステムとの連携によって、注文・会計・販促までの流れをシームレスに自動化する方法についても触れています。
こうした仕組みを導入することで、スタッフの負担軽減や接客品質の安定化だけでなく、経営者自身が新メニューの開発や店舗戦略の立案といった、本来注力すべき業務に時間を割けるようになります。
結果として、顧客満足度の向上と売上アップの双方を実現し、長期的な経営の安定につながるでしょう。今まさに飲食業界は、大きな変化の波を迎えています。この機会にスマセルを導入し、時代に合った店舗運営へと進化させてみませんか。
効率と集客を同時に手に入れ、選ばれ続けるお店づくりを始めましょう。


