人件費率とは、売上に占める人件費の割合を示す経営指標を指し、飲食店の収益性や経営効率を測る重要な数値です。
人件費率が高すぎると、利益が圧迫されてしまい、経営の安定性に影響を与える可能性があります。そのため、サービス品質を維持しながら人件費率を適正な範囲に抑えることが、安定経営の重要なポイントです。
しかし、人件費率の計算は給与や時給以外にも含めるべき項目が多く、正確に把握できていないという店舗も少なくありません。
ここでは、飲食店の人件費率の適正値や計算方法、補助金活用やスタッフ育成、シフト最適化など、離職やサービス低下を招かない削減施策を5つ解説します。
飲食店の人件費率はズバリ何%が適正値?
 飲食店の人件費率は、次の計算式で求められます。
飲食店の人件費率は、次の計算式で求められます。
人件費率 = 人件費 ÷ 売上 × 100
飲食店における人件費率の目安は、業態・地域・店舗規模などの条件によって異なりますが、一般的には売上の20〜30%前後が適正とされます。とくに25〜30%は、サービス品質と利益の両立を図れる理想的な水準です。
この水準を超えても35%以内であれば合格点ですが、上回ると利益が圧迫されやすくなり、経営改善策が必要になる可能性が高まります。
業態による人件費率の違い
高級レストランのように調理や接客に高度な技術や経験が求められる業態では、スタッフ単価や人員数が増え、人件費率は高くなりやすい傾向にあります。
一方、ファストフードやセルフサービス型の飲食店では、調理工程や接客が効率化され、顧客が注文や配膳を行う仕組みが整っているため、必要な人員を最小限に抑えやすく、人件費率も低くなります。
地域による人件費率の違い
都市部では、最低賃金や家賃などの固定費が高く、地方より人件費率が高くなる傾向です。一方地方では最低賃金が比較的低く、固定費も抑えられるため、人件費率が下がる場合があります。
店舗規模による人件費率の違い
小規模店舗はオーナーや店長が調理・接客を兼務することで人件費を抑えやすく、大規模店舗はスタッフ数が増える分、人件費率も上がる可能性があります。
業態、地域、店舗規模という3つの視点から、自店舗に合った人件費率の基準を設定することが重要です。またFLコストとのバランスを考慮することで、安定した黒字でいられる経営の形が整います。
FLコストを60%以内に抑えて黒字経営を目指す
FLコストとは、飲食店の食材費(Food)と人件費(Labor)を合わせた金額のことを指します。
FLコストの内訳
- 食材費(Food):食材や飲み物の仕入れ、調理中の廃棄(ロス)など
- 人件費(Labor):給料や時給、交通費、社会保険料、採用や研修にかかる費用、勤怠管理のシステム費など
店舗を運営するうえで大きな割合を占める費用となっていますが、この数字をうまくコントロールできるかどうかが、安定した経営につながるカギとなります。FLコストの目安は売上の60%以内が適正値とされています。残りの40%で家賃や光熱費、宣伝費などをまかない、利益を残す必要があるためです。FLコストの例
| 業種 | F(材料費) | L(人件費) | FL比率 |
|---|---|---|---|
| 中華料理店 | 31% | 28% | 59% |
| イタリアン・フレンチ店 | 32% | 28% | 60% |
| 寿司屋 | 42% | 24% | 66% |
FLコストを抑えることで、次のようなメリットがあります。
- 利益を出しやすくなる
- メニューの価格を決めやすくなる
- お金の流れが安定しやすくなる
数字を見て食材の使い方や人の配置を工夫すれば、利益を守りながらサービスの質を保てます。「60%以内」という数字は、店舗運用を長く続けるためには守ってほしい目安です。

飲食店の人件費計算で含めるべき7つの項目
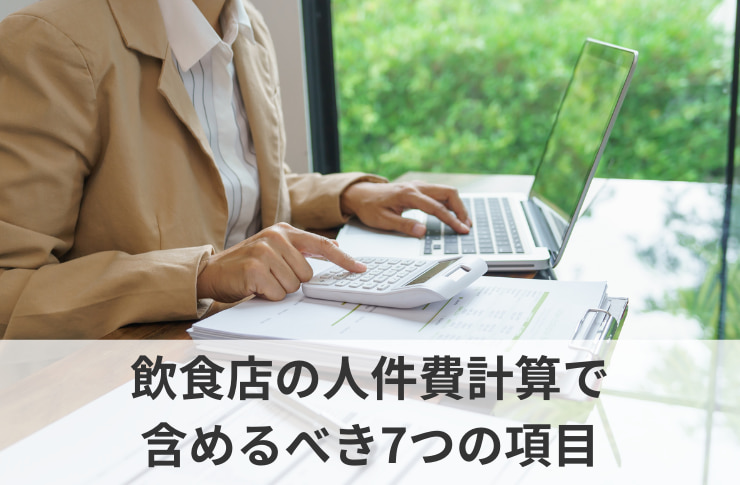 人件費というと、「アルバイトや社員の給料や時給」のみを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、従業員にかかるすべてのコストが対象となります。
人件費というと、「アルバイトや社員の給料や時給」のみを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、従業員にかかるすべてのコストが対象となります。
- 給与:アルバイトの時給や正社員の基本給
- 手当:交通費や役職手当などの各種手当
- 賞与:年数回の賞与やインセンティブなどの特別報酬
- その他:社会保険料や雇用保険料などの法定福利費、退職金や福利厚生費など
他にも、人材を採用する際に発生する求人広告費や面接交通費、入社後の研修費用も人件費の一部です。最近では、勤怠管理やシフト作成に使うシステムの利用料や、労務管理に関する外部サービスの費用も該当します。
これらを計算に入れなかった場合、人件費率は実態より低く見えてしまい、適切な判断や改善策を打つことが難しくなります。「人に関わるお金はすべて人件費に入れる」という意識が、正しい比較や改善の一歩につながります。
以下では、詳細な人件費率を求めるために含めるべき7つの項目を順に解説します。
基本給・時給
基本給・時給は、人件費の中で最も大きな割合を占める項目です。
社員であれば毎月の固定給、アルバイトやパートであれば働いた時間に応じて支払う時給がこれにあたります。また、残業代や深夜勤務手当、休日出勤手当なども含まれます。
飲食店では、ピーク時間帯に合わせて人員を多く配置することが多く、その分の時給が人件費率に直結します。例えば、ランチタイムの混雑時にスタッフを多く入れると売上も伸びますが、人件費も同時に増えます。売上と人員配置のバランスを考えることが、適正な基本給や時給の設定に繋がります。
各種手当
各種手当は、基本給や時給とは別に支払われる追加の報酬です。
代表的なものには、交通費、役職手当、資格手当、住宅手当などがあります。金額は1人あたりではそれほど大きくない場合でも、スタッフ全員分を合計すると、毎月の人件費に大きな影響を与えます。
例えば、全スタッフに一律で支給している交通費や食事補助は、人数が増えるほど総額も膨らみます。こうした手当は、従業員が働きやすい環境を作り、定着率を向上させる効果がある一方で、固定費として常に発生するコストでもあります。
そのため、人件費率を計算するときには必ず各種手当も含め、定期的に内容や金額が現状に合っているかを見直すことが大切です。
賞与・インセンティブ
賞与やインセンティブは、年2回のボーナスや、売上目標を達成したときに支払う報奨金などを指します。
これらはスタッフのモチベーションを高め、店舗の業績向上にもつながる重要な制度です。ただし、賞与やインセンティブは支給額が大きく、支給月に人件費率が上がることがあります。
人件費率を正確に把握するには、こうした費用を月割りや日割りで計算に含めると、年間を通じた本来の人件費率が見やすくなります。
社会保険料
社会保険料には、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの会社負担分が含まれます。
これらは法律で定められているため、削減することはできません。特に正社員を多く雇用している店舗では、この社会保険料が人件費の中で大きな割合を占めています。計算に含め忘れると、人件費率が実際より低く見えてしまうため注意が必要です。
また、スタッフ数や雇用形態のバランスを見直すことで、間接的に負担を抑える方法もあります。
退職金・福利厚生費
退職金は、長く勤めたスタッフへの功労として支払う費用です。
また、制服の支給や食事補助、健康診断などの福利厚生費もここに含まれます。これらはスタッフの働きやすさや定着率を高める効果がありますが、当然ながら人件費として計上されます。
福利厚生は削減しすぎると離職につながる可能性があるため、コストと効果のバランスを考えた運用を心掛けましょう。
採用・研修費
採用・研修費は、新しいスタッフを採用・育成するためにかかる費用です。
例えば、求人広告や採用サイトの掲載料、面接にかかる交通費、入社後の研修やマニュアル作成費用などが含まれます。採用や研修は将来の店舗運営に欠かせない投資ですが、短期間に退職者が多いと費用が無駄になり、人件費率も上昇します。定着率を高める工夫とセットで考えることが重要です。
労務管理・システム費
労務管理・システム費は、勤怠管理や給与計算に使うシステムの利用料、または外部の労務サービスに委託している場合に発生する費用です。
最近ではクラウド型サービスを利用する店舗も増えています。クラウド型サービスの利点は、パソコンやスマートフォンからいつでもデータを確認でき、集計や計算が自動化されることです。
これにより、手作業での計算ミスや集計にかかる時間が減り、本来の店舗運営や接客など多くのことに時間を割けます。月額の費用は数千円〜数万円と比較的少額ですが、年間で見ると無視できない金額になります。
こうした費用も人件費の一部として必ず計算に含め、必要に応じて機能や契約内容を見直すことが大切です。
飲食店の人件費率を下げる5つの施策
 サービスの質や従業員の働きやすさを維持しつつ、人件費率を適切にするための具体的な対策を5つご紹介します。
サービスの質や従業員の働きやすさを維持しつつ、人件費率を適切にするための具体的な対策を5つご紹介します。
- 補助金・助成金の活用
- クロストレーニングで万能型スタッフを育成
- 職場環境の改善で採用・教育コストを下げる
- データ分析でシフトの無駄を削減
- QRオーダーシステムでオーダー業務を効率化
それぞれ詳しく解説していきます。
補助金・助成金の活用
補助金や助成金は、国や自治体が事業者を支援するために提供している制度で、人件費の負担を減らす大きな助けになります。
返済の必要がないため、うまく活用できれば経営にとって非常に心強い資金源です。例えば、新たにスタッフを雇用した際に支給される特定求職者雇用開発助成金、従業員のスキルアップを目的とした研修費用を支援する人材開発支援助成金などがあります。
これらの制度を利用すれば、採用や研修にかかった費用の一部をまかなうことができ、その分人件費率の上昇を防げます。特に、人材開発支援助成金には以下のようなコースがあり、それぞれ電子申請にも対応しています。
- 人材育成支援コース
- 教育訓練休暇等付与コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
それぞれ対象や要件、助成額が異なるため、自店舗の状況や目的に合ったコースを選ぶことが大切です。ただし、制度によって対象条件や申請期限、必要書類が異なります。
手続きをスムーズに進めるには、商工会議所や社会保険労務士など、制度に詳しい専門家へ相談しながら進めると安心です。準備を早めに始めることで、チャンスを逃さず支援を受けやすくなります。
クロストレーニングで万能型スタッフを育成
クロストレーニングとは、スタッフが複数の業務をこなせるように教育する方法です。
例えば、ホールスタッフが簡単な調理やドリンク作りを覚えたり、キッチンスタッフが接客をサポートできるようになったりする状態を目指します。この仕組みを導入すると、混雑時や急な欠勤があった場合でも柔軟にシフトを組めるようになります。
ピークタイムはホールへの人材を増やし、落ち着いた時間帯は仕込みや清掃を進めるなど、状況に応じて人員配置を変えられるのが大きな強みです。また、業務の幅が広がることでスタッフのスキルアップやモチベーションが向上します。
結果として離職率が低下し、新たな人材の採用や教育にかかるコスト削減にもつながります。クロストレーニングは、人件費率の改善と同時に、チーム全体の生産性と働きやすさが高まります。
職場環境の改善で採用・教育コストを下げる
職場環境の改善は、国内外の多くの調査で、職場環境を改善すると仕事上のストレス要因や健康状態が改善し、生産性が向上することが報告されています。
特に、個人向けのストレス対策だけでなく、組織全体で取り組む職場環境改善を組み合わせることが、効果的なストレス軽減につながることが分かっています。日本で導入されているストレスチェック制度でも、職場環境改善の有効性が確認されています。
追跡調査では、職場環境改善を経験した労働者のうち約6割が「自分たちのストレスを減らすのに役立った」と回答しました。
参考:これから始める職場環境改善|厚生労働省
また、ストレスチェックの集団分析を活用して改善を行った企業では、メンタルヘルス不調の発生が減少した事例もあります。
成功のためのポイント
- 経営層の理解とリーダーシップ
- 既存の取り組みや制度を活用する
- 分かりやすい言葉や事例で説明する
- 情報量は最小限に絞る
- 職場の良い点にも目を向ける
- 職場内外の支援者がフォローする
- 結果だけでなく活動の過程も重視する
こうした職場環境改善は、スタッフの定着率を高めると同時に採用や教育コストの削減にもつながります。人件費率の適正化と生産性の向上を同時に実現できる、費用対効果の高い施策といえます。
データ分析でシフトの無駄を削減
シフトを感覚で組んでしまうと、暇な時間帯に人員を配置しすぎたり、忙しい時間帯に人手が足りなくなったりしてしまいます。
こうした配置のズレは、人件費率の無駄な上昇やサービス低下の原因になります。
無駄を減らすには、数字を見ながらシフトを考えることが大切です。例えば、POSレジや勤怠管理の記録を使えば、時間ごとの売上や客数が分かります。こうした分析は、「人時売上高(売上をスタッフの総労働時間で割った数値)」や「人時粗利」といった指標を見ることで、さらに精度が上がります。
つまり、「1人あたり、1時間でどれくらい稼げているか」を数値で把握することが重要です。難しく感じるかもしれませんが、データを見ながらシフトを組むと、忙しい時に十分な人数を配置しながら、落ち着いている時間は少人数で回すことを考えられるようになり、結果として人件費を効率よく使えます。
データに基づくシフト作成は、サービスの質を落とさずに人件費率を下げられるだけでなく、スタッフの負担も減らせます。
QRオーダーシステムでオーダー業務を効率化
QRオーダーシステムは、お客さまが自分のスマートフォンでメニューを見て、そのまま注文できる仕組みです。
テーブルや席に設置されたQRコードを読み取るだけで注文が完了するため、スタッフが注文を取りに行く手間を大きく減らせます。この仕組みを導入すると、ホールスタッフは注文を聞く時間を減らし、その分料理の提供やテーブルの片付け、接客に時間を使えるようになります。結果として少ない人数でも店舗を回せるようになり、人件費率の改善につながります。
また、QRオーダーは注文ミスの防止にも効果があります。お客さまが自分でメニューを選び入力するため、聞き間違いや書き間違いによるミスが減ります。
さらに、注文内容がすぐにキッチンに送られるため、提供までの時間が短縮され、回転率アップにもつながります。導入時には、月額費用や初期費用、必要な機能(多言語対応、写真付きメニュー、在庫連動など)を事前に確認し、自店舗に合ったシステムを選ぶことが大切です。
飲食店の人件費率は「スマセル」で改善
 人件費率を適正に保つためには、注文業務の効率化が重要なポイントになります。
人件費率を適正に保つためには、注文業務の効率化が重要なポイントになります。
そこで役立つのが、次世代セルフオーダーシステム「スマセル」です。「スマセル」は、お客さまのスマートフォンを使ったQRオーダーシステムです。テーブルのQRコードを読み取るだけで、お客さまが自分のスマホから直接注文できるため、ホールスタッフが注文を取りに回る時間を大幅に削減できます。
従来のセルフオーダーシステムとは異なり、専用端末が不要なため初期費用や保守管理費用を抑制し、アプリのダウンロードも必要ありません。導入により、スタッフは注文業務から解放され、料理の提供や清掃、接客により多くの時間を割けるようになります。
スマセルの導入によって、少ない人数でも効率的な店舗運営が可能になり、人件費率の改善につながります。写真付きメニューと多言語対応機能により、増加する訪日外国人にもスムーズな対応が可能です。
また、おすすめメニューの設定やランキング表示、おかわり機能なども搭載し、顧客満足度向上と売上アップにも貢献します。
まとめ
飲食業における人件費率は、一般的に売上の20〜30%が目安とされています。
特に25〜30%の範囲は、利益確保とサービス品質のバランスが取りやすい理想的な水準です。ただし、業態、地域、店舗規模によって適切な人件費率は変動するため、各店舗の状況に応じた基準を設定することが重要です。
人件費を正確に算出するには、給与や時給だけでなく、社会保険料、各種手当、採用・研修費、労務管理費など、従業員にかかる全ての費用を含める必要があります。これにより、FLコスト(食材費と人件費の合計)を60%以内に抑えることが、黒字経営を維持するための大きな指標となります。
人件費率の改善策としては、補助金や助成金の活用、従業員の多能工化を促すクロストレーニング、職場環境の改善、データ分析に基づくシフトの最適化、QRオーダーシステムの導入など、生産性向上に繋がる無理のない工夫が有効です。
特にQRオーダーシステム「スマセル」のような技術を活用すれば、注文業務の効率化により少ない人数でも質の高いサービスを提供できるようになります。お客さまのスマートフォンを使った注文システムにより、ホールスタッフの注文対応時間を削減し、その分料理提供や接客に集中できるため、人件費率の改善とサービス品質の両立を実現できます。
人件費率の適正化を目指すのであれば、「スマセル」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

