飲食業界では、慢性的な人手不足が長年にわたって深刻な課題となっています。
多くの店舗が最低限の人数で営業を続ける中、人件費の高騰も重なり、ワンオペや少人数体制での運営が常態化しているのが現状です。このような状況で最も影響を受けやすいのが、接客品質です。スタッフが不足すると、一人ひとりへの負担が増加し、丁寧な応対が困難になります。
その結果、お客さまへの印象が悪化し、追加注文の機会損失、ネガティブな口コミの拡散、リピート率の低下など、売上を支える基盤となる要素が徐々に悪化する可能性があります。しかし、業界全体の人手不足を短期間で解決することは現実的ではありません。重要なのは、限られた人員の中でも接客品質を維持・向上させる仕組みの構築です。
ここでは、飲食店の接客を取り巻く最新の業界動向から、お客さまが抱きやすい具体的な不満、そして接客品質が売上に与える直接的な影響を解説します。
飲食店の接客で起こっているトレンドの変化

飲食業界では、円安や物価高、人手不足や人件費高騰といった経営課題が続く一方、インバウンドの急増やSNSの影響力拡大といった新たな変化も起きています。
つまり、従来の「日本人客中心」「潤沢な人員配置」を前提とした接客スタイルでは、もはや対応しきれない時代になったということです。変化に適応できない店舗は、機会損失を重ね、競合他社にお客さまを奪われるリスクが高まります。
一方で、新しいトレンドを的確に捉えて接客を進化させた店舗は、より幅広い顧客層を獲得し、持続的な成長を実現できる可能性が高くなります。
多様化する顧客ニーズへの対応
社会情勢の変化に伴い、飲食店では次のような多岐にわたる顧客ニーズへの対応が重要となっています。
| 対応項目 | 現状・必要性 |
|---|---|
| キャッシュレス決済の標準化 | キャッシュレス決済の普及による現金前提の会計フローの見直し |
| アレルギー情報の提供 | メニューでの成分表示・注意喚起やスタッフの適切な対応 |
| ノンアルコールの選択肢拡大 | 酒離れや非飲酒層増加、ドライバーや妊婦への配慮 |
| 食品ロス削減への対応 | 食べ残しの「持ち帰り」における容器や掲示の整備 |
上記のように、従来の「日本人向け・現金決済中心・標準的なメニュー提供」という枠組みを大きく超えた、多くの顧客ニーズに対応することが必要になっています。これまでは一般的な接客マニュアルがあれば十分でしたが、今はお客さま一人ひとりの多様な背景や要望を理解し、きめ細かく配慮したサービスが求められる時代へと変化しています。
すべての要素に完璧に対応することは現実的ではありませんが、自店の立地や客層に合わせて優先順位をつけ、段階的に対応範囲を広げていくことが重要です。
人員削減と丁寧な接客の両立
お客さまの多くは「心地よく過ごしたい」という気持ちで来店されるため、人員不足という店舗の都合に関係なく、質の高い接客を期待しています。人員削減に伴い接客品質が低下すれば、リピート率の悪化につながる可能性があります。
例えば、スタッフが足りないことで以下のような状況が起きれば、満足度の低下により次回の来店意欲が削がれる場合があります。
- 配席や料理の提供が遅れる
- 注文ミスが発生する
- スタッフに声をかけても気づいてもらえない
- お客さまへの声かけが不十分になる
そのため、飲食店は限られた人員でオペレーションを維持しつつ、接客品質を落とさない工夫を迫られています。
お客さまが飲食店の接客に感じる不満とは

実際にお客さまが飲食店の接客に対して抱きやすい不満は以下のとおりです。
- 予約管理とウエイティング対応
- 配膳時の料理の温度や提供スピード
- 注文ミスや配膳の遅れ
- スタッフの口調や勤務態度
接客に対する不満は、単なる気分の問題ではなく、追加注文や口コミ、再来店に直結する重要なポイントです。
予約管理とウエイティング対応
予約や来店時の案内は、お客さまにとってお店の第一印象を決める重要な接点です。
スムーズに席へ案内されるか、待ち時間の説明が丁寧かどうかで、その後の食事全体の印象が左右されます。ぐるなびの「繁忙期のオペレーションの許容範囲」に関する調査によれば、混雑していない状況で不快に感じる接客の1位は「空席があるのに待たされる」(45.7%)、続いて「隣に人がいる席や狭い席に案内される」(44%)という結果でした。
参考:飲食店の繁忙期の接客サービスで不満を感じること|ぐるなび PRO
さらに、予約に関しても「予約時間になっても案内されない」や「予約内容が間違っている」といった不備は、食事の前から不信感を与えてしまいます。特に家族連れや仕事の会食など、大切な場面で利用するお客さまほど、予約対応や入店時の案内には敏感です。
予約やウエイティング対応は単なる事務的な流れではなく、お客さまの心理に直結する重要な時間です。店舗にとっては、待ち時間や案内のストレスを軽減する工夫こそが、満足度の向上とリピート来店につながる第一歩となります。
配膳時の料理の温度や提供スピード
ぐるなびの調査によれば、混雑していない時期の「料理・飲み物の提供」に関する不満の1位は「温かい料理が冷めている・冷たい料理がぬるい」(45.7%)、僅差で「料理が来るのが遅い・待ち時間が長い」(45.4%)という結果でした。混雑していない状況で料理が遅れたり劣化したりすると、来店客は「きちんと管理されていない」と感じやすく、大きなストレスになることがわかります。
参考:飲食店の繁忙期の接客サービスで不満を感じること|ぐるなび PRO
つまり、料理や飲み物の配膳は単にスピードだけでなく、温度管理が求められているのです。お客さまにとっては、その一つひとつが自分を大切に扱ってもらえているかどうかの判断基準になるといえます。
注文・配膳のミス
注文や配膳のミスは、飲食店に対する信頼を大きく損ないます。料理が正しく届かない、忘れられる、提供順序が乱れるといったトラブルは、単なるオペレーション上の不備にとどまらず、お客さまに自分が軽視されているという印象を与えてしまいます。
ぐるなびの調査でも、混雑していないときに不快に感じる接客として「注文した料理・飲み物を間違えられる・忘れられる」が44%、「後から来た客の料理や飲み物が先に出される」が42.6%と高い割合を占めました。さらに「まだ食べている皿やグラスを下げようとする」が42%となっており、どれも自分の食事を邪魔されたと感じる対応が上位を占めています。
参考:飲食店の繁忙期の接客サービスで不満を感じること|ぐるなび PRO
お客さまは混雑による多少の待ち時間には理解を示す一方、不公平感や順序の不透明さには敏感です。自分が後回しにされたと感じる瞬間は、不満を増幅させ、再来店の意欲を削いでしまいます。
スタッフの口調や勤務態度
どんなに料理が美味しくても、スタッフの態度ひとつで店全体の印象は大きく左右されます。接客のマナーや口調は、来店客が快適に過ごせるかどうかを決める重要な要素です。
言い方や声のトーンが少し強いだけでも、入店時や配膳時などシーンを問わず相手に威圧感を与え、不快感を残してしまうのです。忙しい現場ではつい言葉が短くなりがちですが、短いフレーズでも柔らかさを意識するだけで印象は大きく変わります。
また、来店客から見える場所での私語や、複数のスタッフが一箇所に集まって雑談している様子は、接客を軽視している印象を与えてしまいます。お客さまからすれば自分は大切にされていないと感じ、料理やサービスの評価にも悪影響を及ぼします。

飲食店の接客品質が売上に与える影響
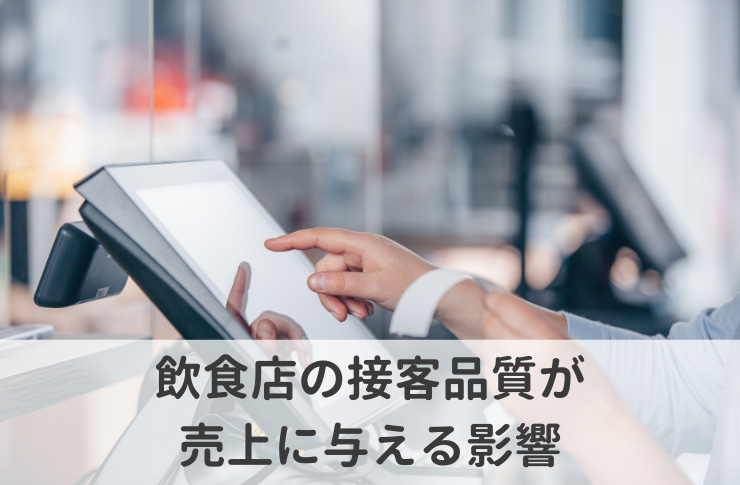
接客品質が実際に売上へどのような影響を与えるのかを具体的に見ていきます。
- 接客の不満による追加注文の減少
- ネガティブな口コミ評価が新規顧客獲得を妨げる
- リピート率低下がもたらす長期収益の悪化
それぞれ詳しく解説していきます。
接客の不満による追加注文の減少
接客の不満は、ちょっとした印象の問題にとどまらず、売上を左右する追加注文のチャンスを失わせます。
例えば、料理や飲み物の提供が遅れたり、スタッフの対応が十分でなかったりすると、お客さまは「これ以上注文しても快適に過ごせない」と感じ、ドリンクやデザートを控えてしまいます。
また、本来なら「もう一杯」「もう一品」と追加注文につなげられる場面でも、スタッフが気づかない、あるいは対応が遅れることで、その機会は失われてしまいます。
そのため、飲食店にとっては、追加注文を逃さないための接客の仕組みをしっかりつくることこそが、売上を維持し伸ばすための大切なポイントです。
ネガティブな口コミ評価が新規顧客獲得を妨げる
飲食店向けの予約サイトやSNSの普及により、来店時の体験が口コミとして可視化されやすくなりました。
結果、ネガディブの口コミが増えることで、来店を検討する新規客にマイナスの印象を与えることになります。株式会社マイスタースタジオの調査によれば、口コミを信じてがっかりした経験がある人は89.4%にのぼります。つまり、口コミは強い影響力を持つ一方で、期待を裏切ると失望感も大きく、新規顧客の信頼を損ねやすいことがわかります。
さらに、「口コミを書く頻度」では、「年1~3回(42.4%)」が最多で、「年に1回未満(31.0%)」と続きました。
7割以上の人が年に3回以下しか口コミを書いていないことから、口コミ投稿は日常的ではなく、特別な行動であるといえます。つまり、ネガティブな口コミは投稿頻度としては少ないものの、一度投稿されれば強い影響力を持ち、検索や比較の段階で新規顧客の来店意欲を削ぐ要因となり得るのです。
参考:飲食店の繁忙期の接客サービスで不満を感じること|株式会社マイスタースタジオ
リピート率低下がもたらす長期収益の悪化
外食業界において、売上の安定を支えているのは新規顧客よりもリピーターです。
新期顧客を呼び込むには求人広告や割引クーポン、SNS広告といった費用が必要となり、一般的に、新規顧客の獲得コストは既存顧客の維持コストの5倍かかるとされています。一方、リピーターは月に2〜3回定期的に来店し、特別な広告費をかけずとも安定した売上をもたらしてくれます。
例えば、月売上300万円の店舗でリピート率が70%から50%に低下した場合、60万円が減少します。売上を補うには、新規顧客の獲得コストを踏まえ、広告費として月20〜30万円の追加投資が必要になると考えられます。
そのため、接客品質が低下してリピーターが離れてしまうと、新規顧客の獲得に依存せざるを得なくなり、広告コストの増加と利益率の低下を招くリスクが高まります。
飲食店の接客品質を向上させる具体的な改善策

接客品質の高い飲食店では、スタッフのスキルに依存しない仕組みづくりと、継続的な改善サイクルの構築により、限られた人員でも一定水準以上のサービスを提供しています。
ここでは、実際に効果が実証されている以下の4つの取り組みを紹介します。
接客マニュアル作成と標準化による品質統一
接客品質の安定化に欠かせないのが、業務の手順を明確にし、共通の基準を持たせることです。
スタッフごとの経験や感覚に任せていては、来店ごとにサービスの質にばらつきが生じ、顧客満足度を損なう可能性があるためです。マニュアルを作成することで、誰が対応しても同じ基準でサービスを提供でき、店舗全体としての信頼性が高まります。特に飲食業界で基本とされる QSC(Quality=料理の品質、Service=接客、Cleanliness=清潔さ) のうち、「Service」を強化する意味でマニュアルは重要です。
例えば、入店時の挨拶、オーダーの確認方法、料理提供時の一言、会計時の対応といった流れを標準化すれば、スタッフは迷わず行動できます。さらに、マニュアルは形だけの存在で終わらせず、定期的に見直すことが欠かせません。
近年のインバウンド増加やキャッシュレス化の浸透など、飲食業界を取り巻く環境は絶えず変化しています。これに合わせて「多言語対応」「機器の操作説明」などを追加すれば、時代に適応したマニュアルとして効果を発揮し続けることができます。
マニュアルの作成と標準化は、単に形式的に用意するものではなく、QSCを可能にする基盤であり、長期的に売上を守る戦略的な取り組みといえます。
定期的な研修による接客技術の向上
接客マニュアルを準備しても、実際の現場でスタッフが同じ水準のサービスを提供できるとは限りません。
そこで重要となるのが、定期的な研修の実施です。
研修を通じてスタッフの理解度を確認し、不足している部分を補うことで、マニュアルが形だけで終わらず、実際の接客に結びつきます。研修内容は、基本的な挨拶や所作にとどまらず、クレーム対応や繁忙時のオペレーションも含めることが効果的です。
例えば、混雑時にどのように声をかければお客さまの不満を軽減できるか、あるいは料理提供が遅れているときに適切な説明やフォローができるかといった実践的な対応力が求められます。また、研修はスタッフのモチベーション維持にも役立ちます。自身の接客スキルが評価され、改善されていると実感できれば、働く意欲が高まり、離職率の低下にもつながります。
近年では動画教材やオンライン研修の導入も進んでおり、忙しい飲食店でも無理なく継続的な教育を行える仕組みが整いつつあります。さらに、定期的な研修は、スタッフ同士で気づきを共有し、店舗全体のQSCを高める文化を根づかせる役割も果たします。
顧客アンケートの実施
接客改善の取り組みを効果的に進めるには、店舗側の判断だけでなく、実際に来店した顧客の声を反映させることが不可欠です。
そのための方法として有効なのが顧客アンケートです。顧客自身が感じた満足点や不満点を収集することで、接客品質の改善点を客観的に把握できます。アンケートでは、外食産業で重視されるQSCを基準に項目を設定すると効果的です。
例えば「料理の温度・味は適切だったか」「スタッフの応対は丁寧だったか」「店内の清潔感は十分だったか」といった質問を設けることで、改善が必要なポイントを数値化して把握できます。また、アンケートの回収方法も工夫が求められます。紙ベースのアンケートは回収率が低くなりやすいため、QRコードやタブレットを活用したデジタル形式にすることで、より多くの意見を集めやすくなります。
さらに、回答者に次回利用できるクーポンを配布することも効果的です。
システムの導入で接客を効率化
飲食業界では、人手不足や来客数の変動に対応するため、システムの導入が急速に進んでいます。
システムの活用は単なる業務効率化にとどまらず、接客品質を安定的に保つための有効な手段となっています。代表例として、モバイルオーダーやタブレット注文システムが挙げられます。導入によって注文の聞き間違いが減少し、スタッフは料理の配膳や顧客への声かけといった「人にしかできない接客」に集中できます。結果的にオーダーミスを防止でき、追加注文の機会も逃さずに済みます。
また、予約管理システムの普及も進んでおり、待ち時間の短縮やスムーズな案内が可能になっています。さらに、顧客データベースと連携させることで、常連客の好みや過去の来店履歴を把握し、よりお客さま一人ひとりにあった接客をできるようになります。
シフト管理や清掃チェックリストをデジタル化することで、スタッフの業務が整理され、作業の抜け漏れを防ぐ効果もあります。このように、デジタルシステムの導入は、効率化と接客品質向上の両立を可能にする取り組みとして、今後さらに重要性を増していくと考えられます。
人手不足と接客品質の両立をスマセルがサポート

飲食店では、限られた人員での運営を余儀なくされる中、「多様化する顧客ニーズへの対応」と「丁寧な接客品質の維持」という2つの課題を同時に解決する必要があります。
しかし、現実的にはこの両立は非常に困難な課題となっています。人手不足に悩みながらも接客品質を向上させたい飲食店の経営者様は、ぜひスマセルをご検討ください。スマセルは、お客さまが自分のスマートフォンでQRコードを読み取り注文を行うシステムです。専用端末の準備が不要で、初期費用を大幅に削減できる点が特徴です。
注文を聞いて厨房に通すまでのフローがなくなることで業務スピードが向上し、スタッフはより重要な接客業務に集中できるようになります。少ない人員でも高品質な接客を維持する環境を実現するためにも、ぜひこの機会にご相談ください。

