深刻な人手不足や人件費の高騰が続く飲食業界では、求人を出しても応募がない、そもそも人を雇えるような余裕がないといった状況が生まれています。
こうした中、多くの飲食店で常態化しているのが、店舗の営業を従業員が1人で回すワンオペレーション(以下、ワンオペ)です。
ワンオペは、開店準備から接客、調理や清掃、事務作業まですべての業務を1人で切り盛りするため、人件費を大幅に削減できる一方で、負担は大きくなります。しかし、飲食業界全体が抱える問題を考慮すると、ワンオペ営業を解消できる可能性は低いのが現実です。そのため、ワンオペを前提とした運営方法を確立し、負担を軽減する取り組みこそが重要になります。
ここでは、ワンオペ営業でも無理なく店舗を回すための4つの効率化施策を解説していきます。
ワンオペ営業の飲食店が抱える深刻な課題

ワンオペ営業の店舗では、一見すると順調に回せていても、以下のような課題を抱えながら運営をしているケースが多くあります。
- 全業務を1人で担当することによる過重な労働負担
- サービス品質と顧客満足度の低下
- セキュリティリスクと緊急時対応の脆弱性
上記の課題は自然に解決されることはなく、むしろ時間とともに深刻化する可能性が高いため、放置すれば店舗運営の継続にも大きな影響を与えかねません。
日常の業務に慣れてしまうと、深刻さを軽視してしまいがちですが、客観的に見直すために改めて整理しておきましょう。
全業務を1人で担当することによる過重な労働負担
飲食店の現場では、仕込み、調理、接客、会計、清掃、発注管理、さらにはSNS更新に至るまで、実に多くの業務が発生します。ワンオペ営業では、これらのすべてを1人でこなさなければならず、精神的・身体的に大きな負担です。
また、ピークタイムを避けて比較的客足が落ち着く時間帯だけワンオペ営業を行っている店舗では、予期しない混雑により対応が追いつかない場面が生じることもあります。ワンオペ営業では、どのような状況が起きても頼れるスタッフがいないため、すべてを1人でこなさなければならなりません。その結果、疲労による体調不良だけでなく、注意が散漫になることで事故やケガのリスクも高まります。
このように、ワンオペの環境は慢性的な長時間労働を助長しやすく、心身の健康を損なうおそれがあります。
サービス品質と顧客満足度の低下
ワンオペ営業では、基本的に複数の業務を並行して進めることはできません。会計と料理の提供が同時に発生すれば、どちらか一方を優先する必要があります。
その結果、どうしてもひとつひとつの対応が遅れてしまい、お客さまを待たせしてしまうことが増えます。現在はSNSやレビューサイトの普及により、こうした「待ち時間の長さ」や「対応の遅れ」に関する口コミが瞬時に拡散され、店舗の評判に大きな影響を与える可能性があります。
また、ワンオペ営業では、飲食店において重要な「おもてなし」の質も低下しがちです。忙しさに追われる中では、お客さま一人ひとりに合わせた丁寧な接客や、細やかな気配りを提供することが困難になります。特に常連客との関係性構築や、初回来店客への親切な案内といった、リピート率向上につながる接客サービスが疎かになりやすく、長期的な売上安定にも影響を及ぼしかねません。
セキュリティリスクと緊急時対応の脆弱性
ワンオペ営業の飲食店が抱える課題の中でも見落とされがちなのが、安全管理と緊急時対応です。
常に「一人きり」であることは、平時には問題がなくても、いざというときには大きなリスクとなります。例えば、営業中に体調を崩して動けなくなった場合には、助けを求めるのにも時間がかかるおそれがあります。特に夜の営業や、厨房と客席を何度も往復するような構造では、誰かの目に留まるまでに時間を要してしまうこともあるでしょう。
酔客とのトラブルや無銭飲食といった問題が発生した際も、適切な対応が難しい場合があります。本来であれば、複数人のスタッフが連携して対応すべき場面でも、ワンオペでは即時の判断と対処をすべて1人で行わなければならず、精神的な負担が大きくなります。
さらに深刻なのは、自然災害などの緊急事態への対応です。火災や地震といった自然災害が発生した場合、お客さまの安全確保や避難誘導を迅速に行う必要がありますが、1人では対応しきれず、むしろ危険な状況を作り出してしまう可能性があります。
このような緊急時には迅速な対応が求められるため、防犯カメラや非常ボタンなどの設備があっても、即座に適切な行動を取ることは困難です。万が一事故や事件が起これば、営業停止や社会的信用の失墜といった深刻な事態を招くおそれもあるため、ワンオペ時の安全管理は店舗の信頼性を左右する重要な課題となっています。

ワンオペ営業の改善が難しい原因
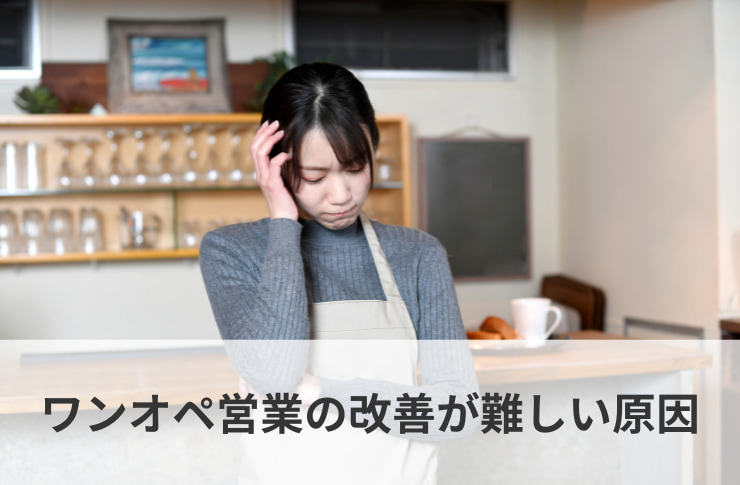
ワンオペ営業の課題は多くの経営者が認識しているところですが、根本的な解決に至らないケースが大半を占めています。この状況の背景には以下のような要因があります。
- 深刻化する人手不足と人材確保
- 業務改善に取り組む時間と余裕の不足
- 限られた予算と投資余力の制約
上記の要因が店舗運営にどのような影響を与え改善を困難にしているのか解説していきます。
深刻化する人手不足と人材確保
飲食業界における人手不足は、もはや個人の努力や工夫だけでは解決できない構造的な問題となっています。
特に小規模店舗では、求人を出しても応募者が集まらない、せっかく雇用してもすぐに離職してしまうという状況が常態化しており、多くの経営者が「人を雇いたくても雇えない」現実に直面しています。この状況は数字でも明確に表れています。
帝国データバンクが2024年に公表した調査では、非正社員の人手不足割合において「飲食店」が64.3%と業種別トップとなりました。これは飲食業界全体が深刻な労働力不足に陥っていることを示しており、個々の店舗の問題ではなく業界全体の構造的課題であることが分かります。さらに深刻なのは、この状況が一時的なものではないという点です。コロナ禍後の需要回復に伴い、人手不足はむしろ悪化の傾向を見せており、2024年以降にわずかな改善が見られるものの、依然として需要と供給のギャップは大きいままです。
参考:人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)|帝国データバンク
このような現実を踏まえると、「いつか良い人材が見つかるはず」「もう少し待遇を良くすれば人が来る」といった期待に頼った経営は、もはや現実的ではありません。そのため、人材確保に頼るのではなく、ワンオペでも無理なく店舗を運営できる仕組み作りにシフトすることが、現実的かつ効果的な解決策と言えるでしょう。
業務改善に取り組む時間と余裕の不足
ワンオペで店舗を運営している場合、1日の大半は接客や調理などの実務に追われます。営業中は目の前の作業をこなすことで精一杯であり、閉店後は片付けや翌日の仕込み、さらには経理や発注作業などが待っています。業務の見直しや改善案を検討するための時間を確保することは、実際には非常に難しい状況です。
また、業務そのものが属人的かつ複雑になっているケースも多く、何をどう改善すればよいかを客観的に把握することが困難です。従業員がいれば分担して振り返りやアイデア出しができますが、1人ですべてを抱えている状況では、現状を整理すること自体が負担になります。業務改善に必要なのは時間だけではなく、冷静な判断力と体力的な余裕も含まれます。精神的・肉体的に疲弊している状態では、効率化や導線設計の見直しといった作業に着手するモチベーションが湧きにくく、つい後回しになりがちです。
その結果として、忙しさが慢性化し、現状を変えるきっかけを失ってしまう店舗も少なくありません。このような悪循環を断ち切るには、「業務の合間に改善策を考える」のではなく、「改善に取り組むための時間を先に確保する」視点が必要です。わずかな時間でも、意図的に確保することが業務の質と効率を見直す第一歩になります。
限られた予算と投資余力の制約
多くの飲食店にとって、ワンオペ営業を改善するうえで最大の障壁となるのが、投資に回せる資金が限られていることです。
日々の営業を続けていくためには、家賃や水道光熱費、食材費、消耗品などの固定的な支出が欠かせません。特に昨今は、原材料価格の上昇や光熱費の高騰といった外部要因も重なり、利益の圧迫が続いています。こうした中で、業務改善のために新しいシステムを導入したり、店舗改装に踏み切ったりするのは、心理的にも経営的にもハードルが高くなります。将来的な効果が期待できるとしても、初期費用の回収までに時間がかかることが多く、投資に対する不安が大きくなりがちです。
また、補助金や助成制度が用意されていたとしても、申請の手間や審査期間、対象条件の複雑さから活用をためらう店舗も少なくありません。経営者自らが現場に立っているケースでは、情報を集める余裕さえ持てないのが実情です。こうした制約下においては、「費用をかけずにできる改善策」や、「小さな投資で効果が見込める取り組み」から着手することが現実的な選択肢となります。
経営における投資判断は慎重であるべきですが、何も変えなければ今後の持続可能性に影響を及ぼすリスクも無視できません。限られたリソースの中で、何に優先して取り組むかを見極める力が、これからの飲食店には求められています。
飲食店のワンオペ営業を効率化する4つの施策

ワンオペ営業における日々の負担を軽減し、無理なく店舗を運営するためには、以下の4つの施策が効果的です。
- シンプルなメニュー構成と調理工程の標準化
- ワンオペに適した店舗デザインと動線設計
- ピークタイム時のスキマバイト活用
- デジタル化による業務の効率化
今すぐ取り組める工夫から、少額の投資で効果を実感できる方法まで、段階的にご提案します。
シンプルなメニュー構成と調理工程の標準化
ワンオペ営業の効率化には、使用する食材や工程を整理し、無駄を省いたメニュー構成が必要になります。
食材を共通化し、複数メニューで使い回せるようにすることで、仕入れと保存の効率化が可能になるためです。例えば、パスタ店であれば基本のトマトソース、クリームソース、オイルベースの3種類のソースを軸に、トッピングを変えることで多彩なメニューを展開できます。また、丼ものの場合は、基本はご飯とメインのおかずを固定し、ソースやトッピングを変えることでバリエーションを増やせます。
また、メインのメニューにサラダとスープを付けたセットや、そこにドリンクを加えたセットといったように、同じ主力商品を軸にしながら構成を工夫することで、客単価のアップと幅広い顧客ニーズへの対応が可能になります。調理や盛り付けも一定の手順で統一し、作業に迷いが生じないようにしておくことで、時間と労力のロスを減らせます。
ワンオペでは、作業量が増えるほど料理の提供時間の遅れや、接客の品質が低下する傾向があります。
しかし、看板商品を中心にした構成へと絞ることで、味やサービスの安定化にもつながります。
ワンオペに適した店舗デザインと動線設計
ワンオペ営業では店内の動線が重要な役割を果たします。
調理スペースから客席、レジ、洗い場といった動線が複雑で移動距離が長いと、それだけで業務に余計な時間がかかるためです。例えば、注文を受けてから料理を提供するまでに「厨房→客席→レジ→洗い場→厨房」と店内を何往復もしていては、その分だけ他の業務が滞ってしまいます。
しかし、ドリンクサーバーを客席の近くに設置したり、客席から直接厨房に移動できる通路を確保できれば、移動時間の大幅な短縮が可能です。また、厨房からホール全体を見渡せるように席配置を調整することで、お客さまへの対応がよりスムーズになります。このように、日々の業務の中で無駄な動きがないかを確認し、改善点を見つけることで業務の効率化が期待できます。
ピークタイム時のスキマバイト活用
近年では、スマートフォンアプリを活用した「スポットワーク」の仕組みが広がっています。
数時間単位で働ける人材と飲食店をマッチングするサービスにより、従来のアルバイト採用よりも柔軟に人材を確保できるようになりました。飲食店で人手が必要になるのは、常時ではなく特定の時間帯に集中することが多くあります。そのため、特にランチやディナーなどのピークタイムに、短時間だけ勤務できるスキマバイトなどを採用するのもおすすめです。
以下は、実際の店舗で行われているスキマバイトの活用例です。
- 昼のピーク時間帯に、配膳と下げ膳を担当するスタッフを2〜3時間だけ導入し、接客負担を軽減
- 土曜夜の混雑時に、レジ・会計業務のみを任せるスタッフを短時間で雇用し、料理提供に専念
- 日祝日のランチ限定で、洗い場作業を中心にサポートする人材を募集し、回転率を向上
特定の業務に絞ってサポートしてもらうことで、少ない人件費で効率的に忙しい時間帯を乗り切ることができます。常時雇用が困難な店舗であっても、必要なときに必要な人材を確保できる柔軟性が、営業の安定性を支える重要なポイントとなります。
デジタル化による業務の効率化
ワンオペの負担を軽減し、日々の業務を効率化するには、注文や会計、予約管理などのデジタル化が欠かせません。
例えば、QRコードを活用したセルフオーダーやキャッシュレス決済の導入は、注文ミスやレジ業務の負担を減らし、1人でもスムーズに店を回せる体制を整える大きな助けとなります。また、営業中にかかってくる予約や問い合わせの電話も、ワンオペでは大きな負担となります。接客や調理に集中したい時間帯と重なりやすく、業務の妨げとなることが少なくありません。
こうした「電話対応の負担を減らしたい」という現場の声に応えて、近年はAI音声による自動応答システムを取り入れる飲食店が増えています。「営業時間のご案内」や「WEB予約への誘導」といった対応を自動で行うことで、着信のたびに手を止める必要がなくなります。録音や文字起こし機能があるサービスを選べば、聞き漏らしの心配も軽減されます。
ほかにも、POSレジや予約台帳アプリ、在庫管理ツールなどを取り入れることで、毎日の業務時間を短縮できます。特別な知識がなくても直感的に使えるものも増えており、以前に比べて導入のハードルは大幅に下がっています。経費をかけずに始められる無料ツールや、補助金を活用できるサービスも豊富に用意されています。こうした工夫を少しずつ取り入れることで、ワンオペ営業でも余裕を持って業務を進められるようになります。
スマセルで飲食店のワンオペ営業を効率化

ワンオペ営業に悩む飲食店に向けて、実際の支援ツールとして注目されている「スマセル」の活用法をご紹介します。
スマセルは、お客さまが自分のスマートフォンを使って注文できる次世代のセルフオーダーシステムです。専用の端末を設置する必要がなく、アプリのダウンロードやパスワード入力などの面倒な手間も一切ありません。
スマセルによる注文や会計の自動化、多言語対応といった具体的な機能が、どのように業務の負担軽減と売上の安定化に貢献するのかを解説します。
注文・会計業務の自動化でワンオペの負担を軽減
ワンオペ営業において、最も負担が集中しやすいのが、注文の受付と会計対応です。
お客さまが来店し、注文を聞き、料理を提供し、会計まで行う一連の流れを、すべて1人で担うのは、時間も神経も使います。スマセルのようなセルフオーダーシステムを導入すれば、注文はお客さまがご自身のスマートフォンで行うことができ、キッチン側に内容が即時に共有されます。これにより、注文ミスや聞き直しの手間が省けるうえ、ピークタイムでも業務が滞りにくくなります。
また、キャッシュレス決済と連動した会計機能を活用することで、現金管理の負担も大きく軽減されます。レジ前の混雑や待ち時間が減ることで、お客さまにとっても快適な体験が提供でき、回転率の向上にもつながります。ワンオペの限界を感じている店舗ほど、このような注文・会計の仕組みを見直すことが、業務全体の見通しを良くする第一歩となります。
多言語対応でインバウンド需要を取り込む
訪日外国人客は年々増加傾向にあり、特に観光地や都市部の飲食店では、英語や中国語での対応が必要となる場面が確実に増えています。
しかし、ワンオペ体制で営業している場合、外国語での対応に時間がかかってしまい、他のお客さまへのサービスが手薄になってしまうといった課題も生じやすくなります。スマセルには、多言語表示機能が標準で搭載されており、英語・中国語・韓国語など、複数の言語をボタンひとつで切り替えることができます。お客さまご自身で母国語の表示を選ぶことで、スタッフが直接対応しなくても、スムーズに注文操作が可能です。
多言語への対応は、外国人観光客にとって安心感を与えるだけでなく、スタッフの精神的な負担も軽減します。少人数体制であっても、インバウンド需要をしっかりと取り込むことができ、売上の拡大や店舗の信頼向上にもつながります。
まとめ
飲食業界における深刻な人手不足は、今後も改善の見込みが立たない状況が続いています。
そのため、ワンオペ営業で運営している飲食店は、この体制を継続していかざるを得ないのが現実です。ワンオペ営業による身体的・精神的な負担は、メニューの簡素化や店内動線の見直し、スキマバイトの活用、予約や注文業務のデジタル化といった取り組みを行うことで、軽減することが可能です。特に注文や会計業務の負担を感じている場合は、スマセルのようなセルフオーダーシステムの導入が効果的です。
お客さまのスマートフォンを使って注文から決済まで完結でき、専用端末の設置も不要なため、初期費用を抑えながら大幅な業務効率化を実現できます。また、多言語対応機能により、インバウンド需要への対応も可能です。ワンオペ営業の課題解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。現在の運営状況をお聞かせいただければ、最適な改善策をご提案いたします。

