近年、インバウンド需要の拡大に伴い、訪日観光客が増加傾向にあります。また、ビジネスや留学、永住などさまざまな理由で日本に住む外国人の数も着実に増えています。
このような背景から、飲食店においては多言語、特に国際共通語である英語メニューの必要性が高まっており、早急な対策が求められています。
しかし、日本料理特有の食材や調理法、文化的背景を持つ料理名は、単純に英語に翻訳しただけでは、外国人には想像しづらい料理も少なくありません。
また、多くの飲食店では日々の営業に追われ、スタッフの人手不足や時間的制約から、英語メニューの作成や更新に時間を割けないという現実的な課題も存在します。
ここでは、外国人客が求める情報の特定から、効率的な英語メニューの作り方、さらに負担を減らすセルフオーダーシステムの活用まで、具体的な解決策をご紹介します。
飲食店が直面する「英語メニュー」の課題
 最近では、AI技術の発達により、高性能な翻訳アプリが次々と登場しています。そのため、飲食店においては日本語が読めない、話せない外国人のお客さまでも、自身のスマートフォンを使ってメニューの内容を理解し、簡単な注文や質問もできるようになりました。
最近では、AI技術の発達により、高性能な翻訳アプリが次々と登場しています。そのため、飲食店においては日本語が読めない、話せない外国人のお客さまでも、自身のスマートフォンを使ってメニューの内容を理解し、簡単な注文や質問もできるようになりました。
しかし、ツールだけでは解決が難しい課題も飲食店の現場には多く存在します。以下の3点を例に挙げて解説していきます。
- 料理や素材を外国人客に伝えることの難しさ
- 日本語メニューでは満たせない外国人客の情報ニーズ
- 時間・人材不足による英語メニュー導入の障壁
特に観光地や都市部の飲食店では、上記の課題を解決することで、外国人のお客さまの満足度が高まり、リピート率や客単価の向上につながる可能性があります。
料理や素材を外国人客に伝えることの難しさ
英語メニューを作成する際、多くの飲食店で直面するのが「料理や食材のニュアンスがうまく伝わらない」という問題です。例えば、フキノトウや自然薯といった日本原産の食材は、英語に直訳できる単語がないか、あったとしても正確なイメージが伝わらないことが多々あります。
こうした食材は、日本人にとっては馴染み深くても、外国人には味や調理法、食感を想像するのが難しいものです。また、料理名も「煮物」「おひたし」「だし巻き卵」など、文化的背景が濃く反映された表現は、英語にした途端に魅力が伝わらなくなってしまう場合があります。
結果として、外国人客がメニューを見ても内容がよくわからず、注文をためらう、あるいは期待と違う料理が出てきたと感じることが起きやすくなります。
このようなミスマッチは、顧客満足度の低下や再来店率の減少につながる恐れがあります。
日本語メニューでは満たせない外国人客の情報ニーズ
日本人であれば、「肉じゃが」や「親子丼」といった名前を見るだけで、どんな食材が使われていて、どんな味なのかが自然と想像できることが多いと思います。
しかし、外国人のお客さまにとっては、料理名だけではイメージできないこともあります。また、翻訳アプリを使用したとしても、和食特有の表現や文化的背景のある料理名は正確に翻訳されないことも多く、混乱を招くケースも少なくありません。
実際に、観光庁が行ったアンケート調査によると、外国人観光客が飲食店で不便を感じる場面で一番多かったのが、「料理を選ぶ・注文するとき」でした。65.8%の人がこの部分に不満があると答えています。つまり、メニューがよくわからないことで、お店選びや注文にストレスを感じているということです。
参考:令和5年度「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート」調査結果│観光庁
そのため、英語メニューを作るときには、料理の写真や説明をくわえることがとても大切です。見てすぐに理解できる工夫を取り入れることが、外国人のお客さまに安心してもらい、また来たいと思ってもらうためのポイントです。
時間・人材不足による英語メニュー導入の障壁
飲食店では仕込みに始まり、お客さまへの丁寧な接客、営業後の念入りな清掃、そして売上や在庫の管理など、一日を通して非常に多くの作業に対応することになります。
このような状況下では、英語メニューの必要性を理解していても、実際に着手するための時間を確保することが難しいというのが、現実ではないでしょうか。
英語メニューの作成においては、単に言葉を置き換えるだけでは不十分で、食材や調理法の文化的な背景を理解した上で適切な表現を選ぶ必要があります。そのため、時間的余裕だけでなく、専門的な知識や経験を持った人材の確保も必要になってきます。
このような複合的な理由から「英語メニューの導入は必要だと認識しているものの、つい後回しにしてしまう」という飲食店も少なくありません。結果として、せっかく来店された外国人のお客さまに十分なサービスを提供できず、リピーターになっていただく機会や、口コミによる新規顧客獲得のチャンスを逃してしまう可能性があるのです。
英語メニューの効率的な作成方法
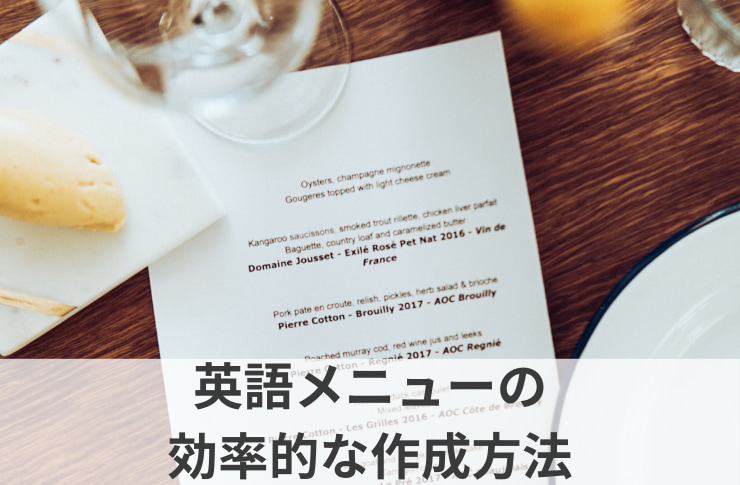 英語メニューを初めて導入する飲食店でもスムーズに取り組める、効率的な作り方のポイントは以下のとおりです。
英語メニューを初めて導入する飲食店でもスムーズに取り組める、効率的な作り方のポイントは以下のとおりです。
- 人気のメニューから優先的に取り組む
- 外国人客がメニューに求める情報を盛り込む
- 料理画像を効果的に取り入れる
上記のポイントを押さえて計画的に進めることで、後々何度もメニューを作り直す手間や、それに伴うスタッフの負担、時間のロスを削減できます。
人気のメニューから優先的に取り組む
英語メニューを作成する場合、すべてのメニューを一度に翻訳しようとすると、時間と労力がかかり頓挫しやすくなります。
そこで、まずお店で特に人気のあるメニューに絞って翻訳を始めてみましょう。人気メニューはすでにお客さまに支持されているため、外国人客にも安心して注文してもらえる可能性が高いためです。
また定番メニューとして長く使われることが多いため、頻繁に修正する必要がなくなり、メニュー更新にかかる手間を省けます。さらに、人気メニューは写真映えするものも多く、画像を添えることで外国人のお客さまにも料理のイメージが伝わりやすくなり、注文につながる可能性が高まります。
まずは、売れ筋メニュー5〜10品ほどに絞り、料理名、簡単な説明文、写真を加えた英語メニューを作成することから始めるのが、現実的かつ効果的です。
外国人客がメニューに求める情報を盛り込む
英語メニューを作る際に大切なのは、ただ料理名を英語に訳すだけではなく、外国人のお客さまが「安心して選べる情報」をしっかり載せることです。日本人には当たり前のように通じる情報でも、外国人には想像が難しいことが多いため、内容を丁寧に伝える工夫が欠かせません。
まず意識したいのが、料理の簡単な説明文です。例えば「豚の角煮」だけでは内容が伝わりませんが、「Braised pork belly simmered in soy sauce and sugar」など、調理法・味付け・特徴を伝える一文があると、外国人にもイメージしやすくなります。
また、各料理に番号を振るのも効果的です。言葉が通じにくい状況でも、注文時に「No.5, please.」と伝えるだけで済むため、お客さまの負担もスタッフのストレスも軽減されます。タブレット注文や紙の注文票にも応用しやすい工夫です。
さらに近年では、アレルギー表示や宗教・食習慣への配慮も大切なポイントになっています。特に欧米や東南アジアからの観光客の中には、卵・乳製品・ナッツ・甲殻類などのアレルゲンに敏感な方や、豚肉やアルコールを避ける方も多くいます。
これに対応するために、以下のような情報を記載することが推奨されます。
- アレルギー表記(含まれる主なアレルゲン)
- 「ベジタリアン対応」「ハラール対応」などの表示
- アルコールや豚肉の有無
たとえば、メニュー下部にアイコンや補足説明を入れることで、文化的な背景の異なるお客さまにも配慮できる店舗であることを印象づけることができます。これにより、安心して食事を選ぶことができ、信頼感や満足度の向上にもつながるでしょう。
料理画像を効果的に取り入れる
英語メニューにおいて、料理の写真を載せることは非常に大きな効果があります。言葉がわからなくても、写真があるだけで「どんな料理か」が直感的に伝わるため、外国人のお客さまにとって安心感が大きく変わってきます。
特に、日本食に馴染みのない観光客の場合、メニュー名や説明文だけでは「何を選べばよいのか」「どんな見た目なのか」が分からず、不安を感じることがあります。そんなとき、料理の実物に近い写真があることで、「これなら美味しそう」「食べてみたい」と判断しやすくなるのです。
さらに、視覚情報があることで、注文ミスの防止にもつながります。たとえば、「唐揚げ」と「チキン南蛮」のように、似た材料でも異なる料理の場合、写真があることで違いが一目でわかり、誤解を防げます。
料理画像を使う際は、以下の点に気をつけるとより効果的です。
- 実際の料理と大きく異ならない写真を使用する
- 一品ごとに写真を載せられない場合は、人気メニューだけでも優先的に掲載する
- タブレット注文の場合は、高画質な画像で拡大表示できる設定が望ましい
こうした工夫をすることによって、言葉の壁を超えて料理の魅力を伝えることができるようになります。結果として、満足度の向上・注文数の増加・SNSでの発信など、さまざまな面でプラスの影響が期待できます。

セルフオーダーシステムで英語メニュー作成の手間を大幅削減
 ここでは、英語メニュー作成や管理にかかる手間を劇的に減らす方法として注目されている「セルフオーダーシステム」の活用法をご紹介します。特にスタッフの人数や時間が限られている飲食店にとっては、多言語対応をしながら、スタッフの負担を軽減できる効率的な方法です。
ここでは、英語メニュー作成や管理にかかる手間を劇的に減らす方法として注目されている「セルフオーダーシステム」の活用法をご紹介します。特にスタッフの人数や時間が限られている飲食店にとっては、多言語対応をしながら、スタッフの負担を軽減できる効率的な方法です。
- 英語以外の言語にも切り替えが可能
- メニューの画像を高画質で表示
- QRコードオーダーシステムなら専用端末が不要
それぞれ詳しく解説していきます。
英語以外の言語にも切り替えが可能
セルフオーダーシステムの大きな魅力のひとつが、メニューの言語をワンタッチで切り替えられることです。英語はもちろん、中国語・韓国語・フランス語・スペイン語など、お店が必要とする言語を事前に登録しておけば、ボタンひとつで表示を切り替えることができます。
たとえば、訪日外国人が来店し、最初に表示されている日本語が読めなくても、「English」や「中文」ボタンを押すだけで、その言語のメニューにすぐに切り替わります。そのため、スタッフが外国語を話せなくても、外国人のお客さまが自分で注文を進めることができます。
このように、多言語に対応したセルフオーダーシステムは、外国人客へのスムーズな接客を可能にし、店舗スタッフの負担も大幅に軽減します。その結果、接客品質のばらつきもなくなり、顧客満足度の向上にもつながります。
メニューの画像を高画質で表示
セルフオーダーシステムのもう一つの大きなメリットは、料理の画像を高画質で表示できる点です。紙のメニューでは写真の大きさや印刷の質に限界がありますが、タブレットやスマートフォンを使ったセルフオーダーなら、画面いっぱいに鮮明な料理写真を表示できるため、視覚的な情報を伝えやすくなります。
外国人のお客さまにとって、言葉だけで料理をイメージするのは難しいことが多くあります。しかし、料理の見た目がはっきり分かれば、「これなら食べてみたい」と感じる判断材料になります。特に日本食は彩りや盛り付けが美しく、写真で魅力を伝えるのに最適です。
また、拡大表示に対応していれば、細かい具材やトッピングまで確認できるので、「何が入っているか分からない」という不安も解消できます。アレルギーをお持ちの方や、宗教上の制限がある方にも安心してもらえます。
高画質な料理写真は、外国人のお客さまの注文率や満足度を高めるだけでなく、SNS映えや口コミ効果による集客力の向上にもつながります。言葉の壁を越えるために、視覚を最大限に活用しましょう。
QRオーダーシステムなら専用端末が不要
最近では、お客さまのスマートフォンを使って注文できる「QRオーダーシステム」が広まりつつあります。
「セルフオーダー」と聞くと、専用のタブレットや高価な機器が必要になる場合がありますが、QRオーダーシステムでは専用端末を準備する必要がありません。
使い方はテーブルにあるQRコードをスマホで読み取り、メニュー画面を表示します。そのあとは、表示された画面で好きな料理を選んでそのまま注文するだけです。画面の言語も切り替えできるので、外国人のお客さまにもわかりやすく、スタッフに頼らずにオーダーできます。
QRオーダーシステムは、お客さまが気兼ねなく注文できる手軽さと、店舗の人手不足や言葉の壁といった負担を軽減できる、双方にとってメリットがあるものです。導入のハードルが低く、すぐに利用できる点も魅力です。
「スマセル」でメニューの多言語対応を強化
 飲食店が複数の言語に対応する方法として、セルフオーダーシステム「スマセル」を紹介します。
飲食店が複数の言語に対応する方法として、セルフオーダーシステム「スマセル」を紹介します。
このシステムは英語だけでなくさまざまな言語に対応しており、外国人のお客さまがストレスなく注文できる環境を提供するとともに、スタッフの負担も軽減します。
対応言語数に制限がなく世界中の外国人客に対応可能
スマセルの大きな魅力のひとつが、表示できる言語の数に制限がないことです。英語・中国語・韓国語といった定番の言語だけでなく、スペイン語やフランス語、タイ語など、必要に応じてさまざまな言語を追加できるため、どんな国の方にも柔軟に対応できます。
例えば、近年増えている東南アジアやヨーロッパからの観光客に対しても、それぞれの言語で料理の内容や注文方法を伝えることができ、「安心して注文できるお店」として信頼を得られます。
また、言語の切り替えもとても簡単で、お客さまがスマートフォンの画面やタブレットでワンタップするだけで自分の言語に変更できるため、スタッフの手を煩わせることなく、スムーズに注文が可能です。このようなシステムがあると、外国語が話せないスタッフでも対応に自信が持てるようになり、現場の雰囲気もぐっと良くなります。
スマセルなら、訪日客の国籍が多様化する中でも、お店側がその都度対応を変えなくて済むので、将来のインバウンドにも安心して備えることができます。
専用アプリ不要で来店後すぐに使える
訪日外国人のお客さまの中には、「日本でスマホが使いづらい」「アプリがダウンロードできなかった」といった困りごとを経験した方も少なくありません。特に海外のSIMカードを日本でローミングして使った場合、通信料が高額になるケースもあり、アプリのダウンロードを避ける人が多いのも現実です。
さらに、日本国内向けのアプリは現地(母国)アカウントではインストールできないこともあります。そのため、「せっかく案内されたけど、注文用アプリが使えなかった」という声もよく聞かれます。
こうした背景を考えると、スマセルのようなアプリ不要のセルフオーダーシステムはとても安心です。テーブルにあるQRコードをスマホで読み取るだけで、ブラウザ上で注文画面が開くので、そのまま料理を選んで注文まで完了できます。
また、操作はわかりやすくシンプルです。レイアウトが工夫されているため、スマホ操作にあまり慣れていない方でも、「メニューを見て、選んで、押すだけ」というわかりやすさがあり、年齢や国籍を問わず使いやすくなっています。
お店側にとっても、「このアプリを入れてください」と説明する必要がなくなるため、スタッフの負担が減り、外国語対応のハードルも下がります。安心して食事を楽しんでもらえる環境づくりに、スマセルはとても役立つ存在です。
専用端末・保守コスト不要で導入できる
多言語対応のセルフオーダーを導入したいと思っても、「設備費が高そう」「機械の管理が大変なのでは」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、スマセルならそうした不安を抱える必要はありません。
スマセルは、お客さま自身のスマートフォンを使って注文してもらう仕組みなので、店舗側で高額な専用端末をそろえる必要はありません。また、タブレットのような機器を置く場合と違って、故障やトラブルのたびに保守対応をする手間や費用がかからないのが大きなメリットです。
導入時も非常にシンプルで、QRコードを設置するだけでスタートできます。初期費用をできるだけ抑えながら、外国人のお客さまにも対応できる体制が整うため、小さな店舗や個人経営のお店でも無理なく始められます。
また、スマセルは多言語表示やメニュー編集の操作も簡単で分かりやすいので、ITに詳しくない方でも安心です。メニューの変更や価格の修正もパソコンやスマホから簡単にできるため、日々の業務の合間でも対応できます。
つまり、スマセルは「設備投資やIT知識がなくても導入しやすい」、そして「長く使っても負担が増えにくい」そんな現場の声に寄り添った仕組みになっているのです。
まとめ
英語メニューとひと口に言っても、ただ翻訳するだけでは伝わらない内容が多いこと、そして外国人のお客さまが安心して注文できる工夫(説明文・画像・アレルギー表記など)が必要であることを押さえておく必要があります。
次に、限られた人手と時間の中で、いかに効率よく多言語対応を進めるかがポイントになります。人気メニューから順に取り組む方法や、写真・説明の整理法、そしてセルフオーダーを活用した作業負担の軽減など、すぐに実践できる工夫がたくさんあります。
中でも「スマセル」は、以下の特長があり、多言語対応に悩む飲食店にぴったりのサービスです。
- 専用アプリ不要でお客さまのスマホだけで使える
- 言語を自由に切り替えられる
- 専用端末が不要で、コストを抑えられる
英語メニューは、単なる翻訳ではなく“おもてなしの一歩”です。外国人のお客さまが「また来たい」と思えるお店づくりのために、今できる小さな工夫から始めてみましょう。

